「朝から大変…着替えだけでクタクタ」
「もしかして、無理な姿勢をさせてないかな?」
「着替えに時間がかかりすぎて、お互いストレス…」
そんな風に感じていませんか?
在宅介護をしていると、毎日の着替え介助は大きな負担になりがちです。たかが着替え、されど着替え。日に何度も行う動作だからこそ、身体的な負担はもちろん、精神的なストレスも溜まりやすいんですよね。
でも、実はちょっとした工夫と知識で、着替え介助の負担は劇的に減らすことができるんです。この記事では、私がこれまで数多くの現場で培ってきた経験と、利用者さんの笑顔を引き出す秘訣を惜しみなく公開します。
今日から実践できる7つの究極のコツと、知られざる介護服の選び方を徹底解説。この記事を読み終える頃には、あなたの介護生活が驚くほど楽になり、もっと笑顔でいられるヒントが見つかるはずです。
介護の負担を劇的に減らす!着替え介助の7つの黄金ルール

介護のイメージ
着替えの介助は、毎日のことだからこそ、知っているかいないかで負担が大きく変わります。ここでは、プロの現場で実践されている、負担を最小限に抑えるための7つの黄金ルールをご紹介します。
ルール1介護者の負担をなくす「着患脱健(ちゃっかんだっけん)」の徹底活用
介護の現場で基本中の基本とされているのが、この「着患脱健」という考え方です。これは、「服を着る時は麻痺や怪我のある患側(かんそく)から着せ、脱ぐ時は健康な健側(けんそく)から脱がせる」という原則です。この順番を意識するだけで、無理な体勢を防ぎ、介助が格段にスムーズになります。
たとえば、右半身に麻痺がある方の場合、着せる時はまず右腕から袖を通し、次に左腕。脱がせる時は左腕から脱がせ、最後に右腕を抜きます。この手順を守るだけで、身体への負担がぐっと減ることを実感できるはずです。
ルール2着替えを成功させる「迎え手」の技術
着患脱健をさらにスムーズにするのが、「迎え手」という手法です。これは、袖やズボンの裾に介護者の手を通しておき、そこに被介護者の手足を迎え入れるようにして服を通す方法です。特に、身体が思うように動かせない方の場合、この手法が非常に有効です。
- まず、介護者が自分の手で服の袖口をしっかりつかみます。
- その手を袖口から服の中に通し、逆側の袖口から手を出します。
- その手で被介護者の腕や手首を優しくつかみ、そのままスッと袖の中に誘導します。
- 最後に、被介護者の手首から手を抜き、もう片方の腕も同じ手順で袖を通します。
この方法を使えば、袖口に手足が引っかかってイライラすることも、無理に引っ張ることもなくなります。
ルール3急がば回れ!時間に余裕を持ったスケジュール管理
時間に追われると、どうしても焦ってしまいますよね。その焦りが、無理な動作につながり、事故や怪我の原因になることも少なくありません。着替えは、最低でも15分、できれば20分程度のゆとりを持って始めましょう。余裕のある介助は、被介護者にとっても安心感につながります。
ルール4危険な場所での着替えは絶対NG
椅子やベッドの端など、不安定な場所での着替えは転倒のリスクが非常に高くなります。介助を始める前に、必ず肘掛けや背もたれのある安定した椅子に座ってもらうか、ベッドの中央で着替えるようにしましょう。特に、ズボンを履く動作はバランスを崩しやすいため、細心の注意が必要です。
ルール5寒い部屋は要注意!着替え時の室温と湿度チェック
着替えの際は、どうしても肌を露出する時間が長くなります。部屋が寒いと、被介護者の体温が下がり、風邪を引いてしまう原因にもなりかねません。特に冬場は、事前に暖房をつけて部屋を暖めておくことが大切です。夏場でも、冷房が効きすぎている場合は、室温を調整してから介助を始めましょう。
ルール6実は危険!全てを介助することの落とし穴
「早く終わらせたいから、全部やってあげよう」という気持ち、わかります。でも、それは被介護者の自立心を奪い、筋力低下を加速させてしまう危険な行為です。時間がかかっても、できることは本人にやってもらいましょう。自分でボタンを留める、袖に手を通すといった小さな動作が、身体機能の維持につながります。
ルール7見逃さないで!着替えは「身体の観察タイム」
着替え介助は、被介護者の全身をチェックできる貴重な機会です。皮膚に赤みやただれ、内出血がないか、特に背中や腰、お尻といった褥瘡(床ずれ)ができやすい部分を念入りに観察しましょう。毎日チェックして記録しておくと、肌の変化にすぐに気づくことができ、早期の受診につながります。
選ぶ服で介護が変わる!プロが推す「究極の介護服」選び
着替えの負担を減らすには、介助のコツだけでなく、「どんな服を選ぶか」も同じくらい重要です。ここでは、介護の現場で重宝されている、着替えが劇的に楽になる介護服の選び方を解説します。
着替えやすさが段違い!介護服が持つ4つの特徴
一般的な服と介護服には、明確な違いがあります。特に注目すべきは、以下の4つのポイントです。
- 前開きや横開き頭からかぶるタイプではなく、ボタンやマジックテープで前や横が大きく開くデザインは、寝たきりの方でも楽に着替えさせることができます。
- ゆったりとしたサイズ感袖や足を通す際に、窮屈だと時間がかかり、身体にも負担がかかります。少しゆとりのあるサイズを選ぶことで、スムーズな着脱につながります。
- 滑りの良い素材袖を通しやすいよう、滑りの良い素材を選ぶことも大切です。コットンやシルク、レーヨンといった素材がおすすめです。
- 縫い目がない、もしくはフラットな縫い目ベッドで過ごす時間が長い方の場合は、背中側の縫い目やタグが刺激となり、褥瘡の原因になることがあります。縫い目のないシームレスな肌着や、縫い目がフラットなものを選びましょう。
これらの特徴を持つ服を選ぶことで、着替えにかかる時間が半分以下になることも珍しくありません。
【目からウロコ】裏表がない「リバーシブル肌着」の秘密
「裏表がない服なんてあるの?」と思うかもしれませんが、実は介護用の肌着には、裏表どちらからでも着られるリバーシブル仕様のものがあります。この「裏表がない」というシンプルな機能が、介助の現場では絶大な効果を発揮します。
バタバタと慌ただしい着替えの際に、いちいち裏表を確認する手間がなくなり、時間短縮につながります。また、利用者さんが自分で着替える際も、裏返っていても気にせず着られるので、自立を促すことにもつながります。
介護服の着替えに関する疑問解決Q&A
Q1: 介護用の服って、普通の服と比べてどう違うの?
A: 介護用と銘打たれている服は、着替えのしやすさと被介護者の身体への配慮が徹底的に考えられています。例えば、腕や脚の関節が固まっていても着せやすいように、袖口や裾が広く作られていたり、マジックテープやスナップボタンで簡単に開閉できるものが主流です。また、寝たきりの方の場合は、背中に縫い目がないなど、褥瘡(床ずれ)を防ぐための工夫もされています。
Q2: どんな時に介護服に切り替えるべき?
A: 以下の兆候が見られたら、介護服への切り替えを検討する良いタイミングです。
- 普通の服を着せようとすると、被介護者が痛みを訴える。
- 着替えに20分以上かかるようになった。
- 着替えを嫌がるようになったり、拒否するようになった。
- 服の着脱時に、転倒しそうになるなど危険を感じるようになった。
これらのサインは、今の服や着替え方法が身体に負担をかけている証拠です。早めに切り替えることで、お互いのストレスを軽減できます。
Q3: 介護服はどこで買えますか?
A: 主に、以下のような場所で購入できます。
- 介護用品の専門店多くの種類があり、専門の相談員がいる場合も多いです。
- 大手衣料品店の介護コーナー近年、ユニクロや無印良品などでも介護・高齢者向けの商品が増えています。
- オンライン通販品揃えが豊富で、自宅にいながら比較検討できます。商品のレビューも参考になります。
実際に手にとって素材や着脱のしやすさを確認したい場合は、実店舗に足を運ぶことをおすすめします。
今すぐ介護の悩みを解決したい!どうしたらいい?

「親族の介護、もう待てない状況になっていませんか?」
介護は突然やってきます。「まだ大丈夫」と思っていても、転倒や急な体調変化で一気に現実となることも。
そんな時、慌てて施設を決めて後悔しないために。
もちろん、今介護で悩んでいる人であってもどの施設であればすぐに入れるのかを事前に情報収集する必要があります。
そんなとき「みんなの介護」なら、業界最大手の安心感と51,000件という圧倒的な選択肢で、あなたがどんな状況でもベストな施設が見つかります。
⭐ 掲載施設数No.1の実績
⭐ 経験豊富な相談員が24時間サポート
⭐ 見学予約から入居まで完全無料でフォロー
「あの時、もっと調べておけば良かった」
そんな後悔をしないために、今すぐ行動を。
複数施設の資料を取り寄せて、ご家族で安心できる選択をしませんか?
▼無料資料請求はこちら▼
資料請求はこちら
![]()
まとめ|介護は「頑張る」より「楽にする」が長続きの秘訣
いかがでしたか?
着替えの介助は、日々の生活の中で何度も繰り返される、いわば「介護の日常」そのものです。だからこそ、ちょっとした工夫と知識で、その負担は劇的に変わります。
介護は「頑張る」より「楽にする」が長続きの秘訣です。今回ご紹介した7つの黄金ルールと究極の介護服選びをぜひ日々の生活に取り入れてみてください。被介護者の笑顔が増え、あなた自身の心にもゆとりが生まれることを願っています。


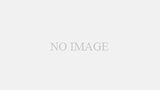

コメント