「介護保険の改正っていつから始まるの?」「うちの事業所は何を準備すればいいの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?2024年度の介護保険改正は、過去最大規模の変更点を含んでおり、知らないままでは事業運営に大きな影響が出る可能性があります。
この記事では、介護保険改正の施行時期から具体的な変更内容、そして実務での対応方法まで、介護事業所の経営者や現場スタッフの方々が本当に知りたい情報を分かりやすく解説します。特に多くの方が見落としがちなサービス種別による施行日の違いや、報酬改定率の内訳については詳しくお伝えしていきます。
介護保険改正の施行日は2つに分かれている

介護のイメージ
2024年度の介護保険改正で最も重要なポイントは、施行日がサービス種別によって異なるという点です。これを知らずに準備を進めてしまうと、対応が間に合わない事態になりかねません。
2024年4月施行のサービス
大半のサービスは2024年4月1日から新制度が適用されています。訪問介護、通所介護(デイサービス)、居宅介護支援、認知症対応型通所介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与など、多くの事業所が利用する主要なサービスがこちらに該当します。
これらのサービスを提供している事業所は、4月から新しい報酬体系での請求が必要になっており、システム改修や職員への周知も4月に間に合わせる必要がありました。
2024年6月施行のサービス
一方、診療報酬改定と連動するサービスは2024年6月1日からの施行となっています。具体的には、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導の4つのサービスです。
これらは医療との連携が強いサービスのため、診療報酬改定のタイミングに合わせて施行日が設定されました。つまり、これらのサービスを提供している事業所は、4月施行の事業所よりも2か月の猶予があったことになります。
2024年度介護報酬改定率の全体像
今回の改定率はプラス1.59%という数字が発表されていますが、実はこれだけでは全体像が見えません。内訳を正しく理解することが、事業所の収益予測には不可欠です。
改定率の詳細な内訳
プラス1.59%の内訳は、介護職員の処遇改善分がプラス0.98%、その他の改定率がプラス0.61%となっています。処遇改善に約6割が配分されていることから、国が介護人材の確保と定着を最重要課題と位置づけていることが分かります。
さらに注目すべきは、改定率の外枠としてプラス0.45%相当の増収効果が見込まれている点です。これは処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収を指しています。つまり、実質的には合計でプラス2.04%相当の改定と捉えることができるのです。
他の報酬改定との比較
2024年度は介護報酬だけでなく、診療報酬と障害福祉サービス等報酬も同時に改定される、いわゆるトリプル改定の年でした。診療報酬の改定率はプラス0.88%、障害福祉サービス等報酬の改定率はプラス1.12%(外枠を含めるとプラス1.5%)となっており、介護報酬の改定率が最も高い水準となっています。
これは高齢化の進展と介護人材不足という社会的課題の深刻さを反映しているといえるでしょう。
4つの改定の基本方針と具体的な変更点
今回の介護保険改正は、4つの大きな柱に基づいて進められました。それぞれの方針を理解することで、なぜこのような変更が行われたのかが見えてきます。
地域包括ケアシステムの深化と推進
高齢者が住み慣れた地域で最後まで暮らし続けられる社会を実現するため、医療と介護の連携強化が重点的に進められています。具体的には、訪問看護と訪問介護の連携を評価する加算の新設や、居宅介護支援事業所による医療機関との情報共有を促進する仕組みが導入されました。
また、認知症の方への対応力を高めるため、認知症専門ケア加算の要件見直しや、認知症対応型サービスの報酬体系の見直しも行われています。
自立支援と重度化防止に向けた取り組み
介護サービスの目的は、単に日常生活の支援をすることだけではありません。利用者の自立を支援し、要介護度の悪化を防ぐことこそが本来の目的です。
今回の改定では、科学的介護情報システム(LIFE)への情報提出とフィードバックの活用を評価する仕組みが拡充されました。データに基づいた介護の質の向上を目指す事業所には、より高い報酬が設定されています。
働きやすい職場づくりの推進
介護人材の確保は業界全体の課題です。今回の改定では、処遇改善加算の一本化が大きなトピックとなりました。従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3つが統合され、より使いやすく効果的な仕組みに生まれ変わっています。
また、業務効率化やICT活用を評価する加算も拡充され、介護現場の生産性向上を後押しする内容となっています。介護ロボットの導入支援や、テクノロジーを活用した見守りシステムの評価なども盛り込まれました。
制度の安定性と持続可能性の確保
高齢化が進む中で、介護保険制度を将来にわたって維持していくためには、効率的なサービス提供が求められます。今回の改定では、過剰なサービス提供を抑制し、本当に必要な人に必要なサービスが届くような仕組みづくりが進められています。
具体的には、区分支給限度基準額の管理の適正化や、福祉用具貸与の価格の透明性確保などが盛り込まれました。
事業所が今すぐ確認すべき対応事項
改正内容を理解したら、次は実務での対応です。特に以下の3点は必ず確認しておきましょう。
まず、自事業所の提供サービスの施行日を再確認してください。4月施行と6月施行では準備期間が大きく異なります。複数のサービスを提供している事業所は、それぞれの施行日を個別に把握する必要があります。
次に、請求システムの改修状況を確認しましょう。多くの事業所が介護ソフトを使用していますが、改定対応のバージョンアップが必要です。請求ミスを防ぐためにも、システムベンダーとの連携を密にしてください。
最後に、職員への周知と研修です。特に処遇改善加算の一本化については、職員から質問が出ることが予想されます。給与への影響や評価制度の変更について、丁寧な説明が求められます。
介護保険改正いつからに関する疑問解決
なぜサービスによって施行日が違うのですか?
診療報酬と密接に関連するサービスについては、医療機関との連携や整合性を保つため、診療報酬改定と同じ6月施行とされました。訪問看護や訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導は、医師の指示や医療機関との情報共有が必要なサービスであるため、診療報酬と同時に改定することで混乱を避ける狙いがあります。
改定率がプラスということは収益が増えるのですか?
必ずしもそうとは限りません。改定率がプラスでも、加算の算定要件が厳しくなったり、基本報酬が下がるサービスもあります。また、処遇改善分の0.98%は職員の給与に充てることが前提となっているため、事業所の利益として残るわけではありません。個別のサービスごとに報酬の増減を確認し、経営への影響を試算することが重要です。
小規模事業所でも対応できますか?
今回の改定では、小規模事業所への配慮も盛り込まれています。ICT化や業務効率化への支援、処遇改善加算の簡素化など、小規模でも取り組みやすい仕組みが整備されました。ただし、情報収集と計画的な準備は欠かせません。地域の介護事業者団体や自治体の相談窓口を活用することをおすすめします。
今後また改正はありますか?
介護報酬は原則として3年に1度改定されます。次回の改定は2027年度の予定です。ただし、社会情勢の大きな変化があった場合は、臨時の改定が行われることもあります。常に最新情報をチェックし、変化に対応できる体制を整えておくことが大切です。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
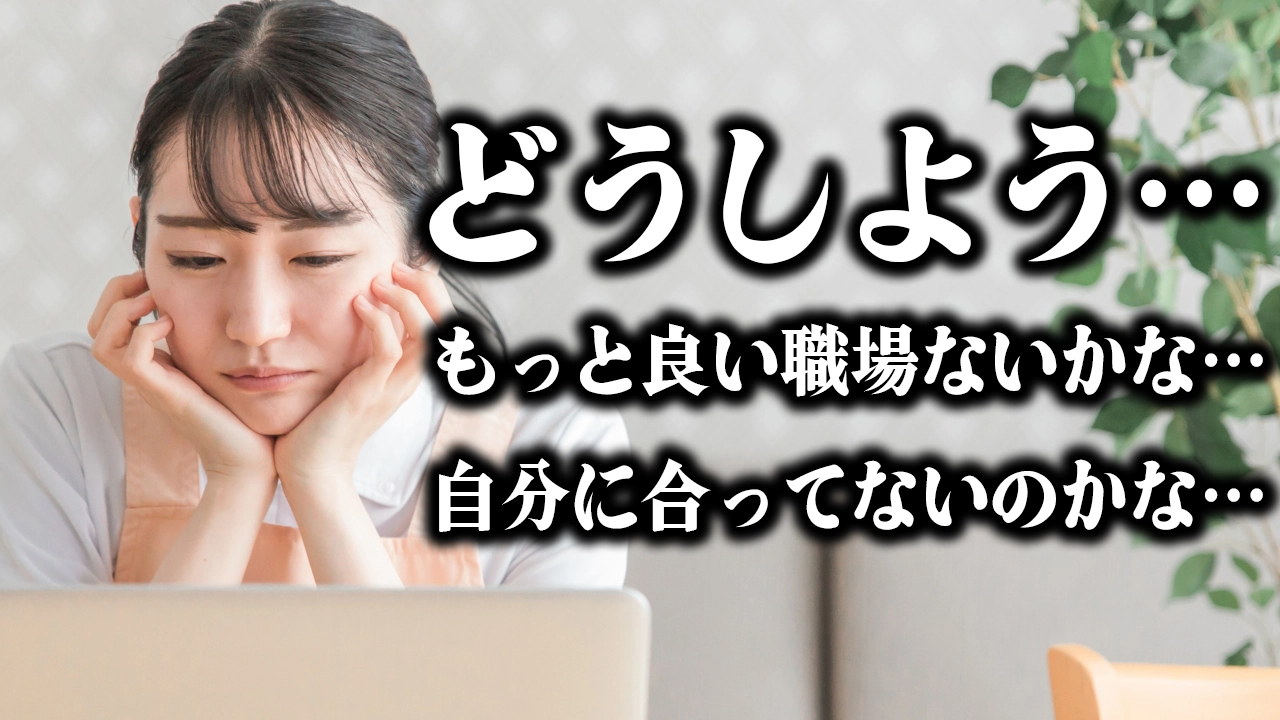
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ
2024年度の介護保険改正は、4月と6月の2段階で施行されています。改定率はプラス1.59%ですが、外枠を含めると実質プラス2.04%相当の改定となっており、特に処遇改善に重点が置かれています。
地域包括ケアの推進、自立支援の強化、働きやすい職場づくり、制度の持続可能性という4つの柱に基づいた改正内容を理解し、自事業所のサービスに応じた適切な対応を進めることが重要です。施行日の確認、システム対応、職員への周知という3つのステップを着実に実行していきましょう。
介護保険制度は常に進化しています。今回の改正を単なる負担と捉えるのではなく、サービスの質を向上させ、職員の働きやすさを改善する機会として前向きに取り組んでいくことが、これからの介護事業所には求められています。




コメント