訪問看護ステーションを運営されている方、またはこれから開業を考えている方にとって、2025年3月に発表された介護保険制度の改正内容は見逃せない重要な情報です。中央社会保険医療協議会(中医協)で了承された新しい指導の仕組みは、今後の訪問看護業界全体に大きな影響を与えることになります。特に年間請求額が高額な事業所や、1件あたりの請求単価が高いステーションは、新たな指導対象となる可能性があります。この記事では、何が変わるのか、なぜ変わるのか、そして今後どう対応すべきかを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
介護保険改正で訪問看護ステーションに何が起きているのか

介護のイメージ
訪問看護は、医療と介護の両方のニーズを持つ高齢者が自宅で生活を続けるために、なくてはならないサービスです。がん末期の患者さんが最期を自宅で過ごしたいという希望を叶えたり、退院直後の不安定な状態の患者さんをサポートしたりと、その役割は年々重要性を増しています。
しかし、訪問看護の需要が高まり、診療報酬や介護報酬での評価が充実してきた一方で、深刻な問題も浮上してきました。2018年度から2023年度にかけて、年間医療費が2億5000万円以上の大規模ステーションが実に1280%も増加しているのです。これは年間医療費1500万円未満のステーションの増加率122%と比べると、驚異的な伸びと言えます。
さらに注目すべきは、レセプト1件あたりの平均医療費が50万円以上のステーションが717%増加している点です。同じ期間で平均費用額が10万円未満のステーションは136%の増加にとどまっています。
もちろん、請求額が多い、単価が高いからといって、すぐに「不適切なサービスを提供している」というわけではありません。大規模なステーションでは利用者が多いため請求額が大きくなるのは当然ですし、重症者への対応を積極的に行っているステーションでは単価が高くなるのも自然なことです。
なぜ今、訪問看護の指導が厳格化されるのか
厚生労働省が指導の仕組みを強化する背景には、一部の訪問看護ステーションで見られる不適切な運営実態があります。最も問題視されているのが、利用者の状態に関係なく、一律に上限回数まで訪問看護を行っているケースです。
訪問看護には適切な回数の設定があります。医療保険の訪問看護では原則として週3日以内、末期がんや重症筋無力症などの特定疾患では制限なしとされていますが、これはあくまで上限であり、「上限まで使わなければいけない」という意味ではありません。本来は、訪問看護師が利用者や家族の状況を把握した上で、主治医の指示書に基づいて適切な回数を決定すべきなのです。
しかし現実には、訪問に直接携わっていない事業所の開設者や経営者が、利益を優先して訪問回数を決めているケースが指摘されています。特に精神科訪問看護での過剰訪問が問題となっており、2024年10月には厚生労働省から「指定訪問看護の提供に関する取扱方針について」という事務連絡が出され、注意喚起が行われました。
それでも、現在の指導体制には大きな課題があります。指導や監査を行うきっかけが主に「利用者や家族からの情報提供」に限られているため、問題があっても表面化しにくいのです。実際、2018年度から2023年度までの指導件数は年間わずか7件から20件程度にとどまっています。
また、株式会社などが複数の都道府県にまたがって広域展開している場合、各都道府県での情報共有が不十分で、実態把握が困難という問題もありました。
新しい指導の仕組み3つの柱となる改革
こうした課題を解決するため、中医協で了承された新しい指導の仕組みは、大きく3つの柱で構成されています。
まず第一の柱は、広域運営されている訪問看護ステーションへの効果的な指導体制の構築です。これまでは都道府県ごとに指導が行われていたため、複数の都道府県で事業展開している企業に対して統一的な指導ができませんでした。新しい仕組みでは、厚生労働省本省、地方厚生局、そして都道府県が連携して指導を行います。これにより、ある県での指導内容が他の県にも横展開され、より効果的な指導が可能になると期待されています。
第二の柱は、教育的な視点による指導機会の確保です。これまでは主に情報提供があった場合にのみ指導が行われていましたが、新制度では一定の基準に該当するステーション、例えば高額な請求を行っている事業所に対して、予防的・教育的な観点から指導を行うようになります。保険者や審査支払機関からの積極的な情報提供も促進され、問題が深刻化する前に早期発見・早期対応が可能になります。
第三の柱は、集団指導のeラーニング化です。現在、講習形式で実施されている集団指導をオンライン化することで、訪問看護ステーションの受講機会を増やし、利便性を高めます。忙しい現場スタッフでも、時間と場所を選ばずに必要な知識を習得できるようになるのです。
これらの改革は2025年度の早い時期に通知改正が行われ、実際に適用される予定です。訪問看護ステーションに係る指導要綱の改定という形で、具体的な基準や手続きが定められることになります。
訪問看護ステーションが今すぐ取るべき対策
新しい指導制度への対応として、訪問看護ステーションの経営者や管理者が今すぐ始めるべきことがあります。
最も重要なのは、サービス提供の実態を正確に記録し、説明できる体制を整えることです。訪問回数や時間、訪問する人数について、なぜその設定が必要だったのかを明確に説明できるよう、利用者ごとの状態評価と訪問計画の根拠をしっかりと文書化しておきましょう。特に、主治医からの訪問看護指示書の内容と実際のサービス提供が整合しているか、定期的に確認することが大切です。
次に、現場の看護師が適切に判断できる仕組みづくりが必要です。訪問看護の日数や回数は、実際に利用者や家族と接する看護師が、その都度の状況を見て判断すべきものです。経営者や管理者が一律に回数を決めたり、営業目標のために不必要な訪問を強いたりすることは、新しい指導要綱で明確に禁止されています。現場の看護師が専門職として適切な判断を下せるよう、教育体制とサポート体制を整備しましょう。
また、定期的な内部監査の実施も効果的です。外部から指導を受ける前に、自分たちで問題点を発見し改善する体制があれば、より質の高いサービス提供につながります。レセプトデータを分析し、自事業所の請求額や単価が同規模の他事業所と比べてどうなのか、客観的に評価することも重要です。
さらに、多職種との連携強化も忘れてはいけません。主治医、ケアマネージャー、他の介護サービス事業者との密接な連携があれば、利用者にとって本当に必要なサービスが何かが明確になります。過剰でも不足でもない、適切なサービス提供が実現できるのです。
介護保険改正と訪問看護に関するよくある質問
年間請求額が高いと必ず指導対象になるのですか
いいえ、年間請求額や単価が高いからといって、自動的に問題視されるわけではありません。大規模に運営していたり、重症患者への対応を積極的に行っていたりすれば、自然と請求額は高くなります。重要なのは、その請求内容が適切かどうかです。利用者の状態に応じた必要なサービスを提供し、それを適切に記録・説明できていれば問題ありません。新しい指導制度は、不適切な運営を行っている一部の事業所を発見することが目的であり、真摯に運営している事業所を萎縮させることが目的ではないのです。
eラーニングによる集団指導はいつから始まりますか
具体的な開始時期は今後の通知で明らかになりますが、2025年度の早い時期に制度が整備される予定です。eラーニング化により、これまで参加が難しかった小規模事業所や遠隔地の事業所でも、質の高い研修を受けられるようになります。受講の利便性が高まることで、より多くのスタッフが最新の知識を学ぶ機会が増え、業界全体のサービス品質向上につながることが期待されています。
複数の都道府県で展開している場合の指導はどうなりますか
新制度では、厚生労働省本省と地方厚生局、そして各都道府県が連携して指導を行う体制が構築されます。これにより、ある都道府県で指摘された問題点が他の都道府県の事業所にも共有され、全体として統一的な改善が促されます。広域展開している企業にとっては、各地でバラバラな対応をする必要がなくなり、かえって効率的な運営改善が可能になる面もあると言えるでしょう。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
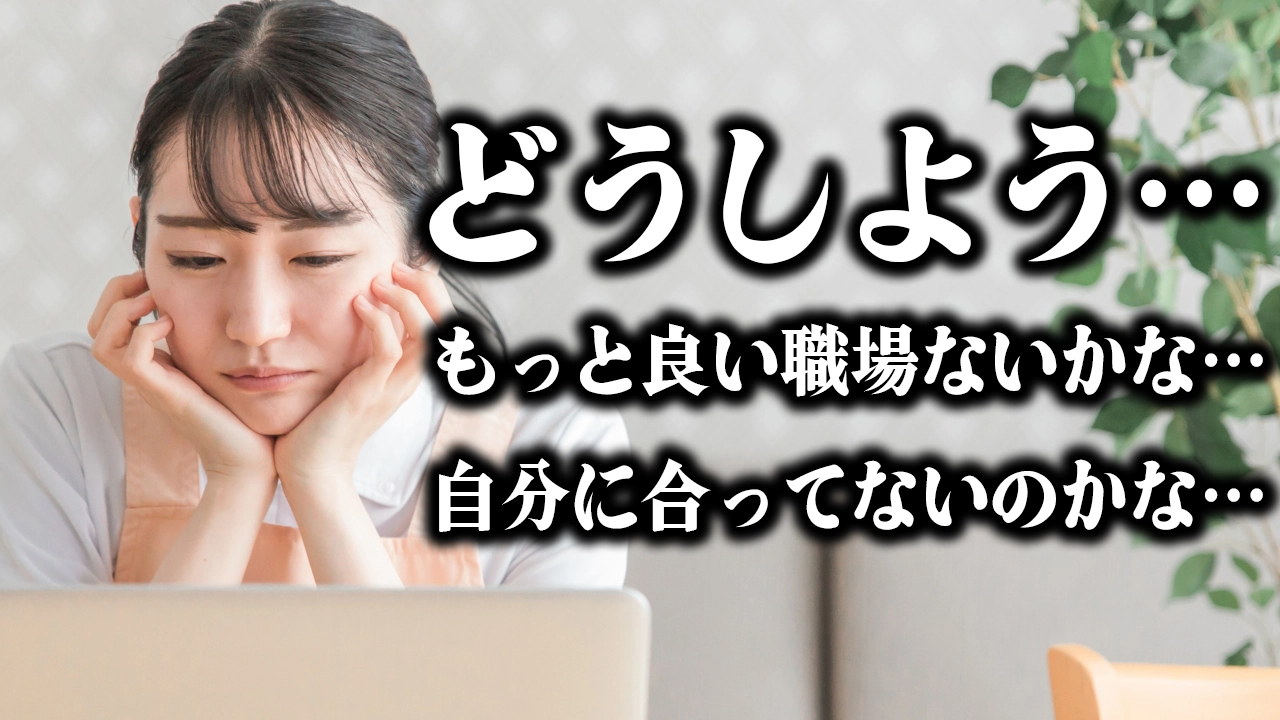
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ
2025年の介護保険制度改正による訪問看護の新しい指導体制は、業界全体の質を向上させるための重要な転換点です。広域運営への対応強化、教育的視点による指導機会の確保、そしてeラーニング化という3つの柱により、より効果的で公平な指導が実現されます。
この変化を「規制強化」と捉えるのではなく、「適切なサービス提供を後押しする仕組み」として前向きに受け止めることが大切です。多くの訪問看護ステーションは、日々質の高いサービス提供に尽力しており、一部の不適切な運営を行う事業所のために、業界全体の信頼が損なわれることは避けなければなりません。
今こそ、自事業所の運営を見直し、より透明性の高い、利用者本位のサービス提供体制を構築する好機です。現場の看護師が専門職として適切な判断を下せる環境を整え、多職種との連携を強化し、内部監査を徹底することで、新しい指導制度にも自信を持って対応できるでしょう。訪問看護の社会的役割はますます重要になっています。この改正を機に、業界全体がさらに発展していくことを期待しましょう。




コメント