介護保険制度の改正について調べていて、「結局、要支援の私はどうなるの?」と不安を感じていませんか。特に要支援認定を受けている方やそのご家族にとって、制度改正は生活に直結する重要な問題です。この記事では、介護保険改正が要支援にもたらす具体的な影響を、初心者の方にもわかりやすく解説します。複雑に見える制度改正も、ポイントを押さえれば決して難しくありません。あなたの不安を解消し、今後の介護生活をより良いものにするための知識をお届けします。
介護保険制度における「要支援」とは何か

介護のイメージ
まずは基本から確認していきましょう。介護保険制度では、介護が必要な度合いによって要支援1・2と要介護1~5の7段階に分類されています。要支援は、日常生活はほぼ自立しているものの、少しの支援があればより安全で快適に暮らせる方が対象となります。
要支援1は、立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な状態です。一方、要支援2は要支援1よりも少し支援が必要で、身の回りの世話の一部に介助が必要になる状態を指します。要支援と要介護の最大の違いは、要支援が「介護予防」に重点を置いているという点です。つまり、今の状態を維持・改善することで、要介護状態への進行を防ぐことを目的としています。
要支援認定を受けると、介護予防サービスを利用できるようになります。これには訪問介護、通所介護(デイサービス)、福祉用具のレンタルなどが含まれますが、要介護の方が受けられるサービスとは内容や利用方法が異なる点に注意が必要です。
2024年~2025年の主要な介護保険改正内容
介護保険制度は3年ごとに見直しが行われており、直近では2024年度に重要な改正が実施されました。この改正は2025年現在も私たちの生活に大きな影響を与え続けています。
第一の改正ポイントは、介護報酬の改定です。介護サービス事業者に支払われる報酬が見直され、これにより提供されるサービスの質や内容にも変化が生じています。特に要支援者向けの介護予防サービスについては、より効果的な自立支援を促進するための仕組みが強化されました。
第二の改正ポイントは、利用者負担の見直しです。一定以上の所得がある方については、自己負担割合が見直される可能性があり、これまで1割負担だった方が2割や3割負担になるケースも出てきています。要支援認定を受けている方の中にも、所得状況によっては負担が増加する可能性があるため、ご自身の負担割合を確認することが重要です。
第三の改正ポイントは、地域支援事業の充実です。要支援者向けのサービスの一部が、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)として市町村が主体となって提供される形に移行しています。これにより、地域の実情に応じたきめ細かいサービスが受けられる一方で、住んでいる自治体によってサービス内容に差が生じる可能性もあります。
要支援認定者への具体的な影響と対応策
では、これらの改正が要支援認定を受けている方に具体的にどのような影響をもたらすのでしょうか。ここでは実生活に直結する重要なポイントを解説します。
サービス内容の変化と選択肢の拡大
総合事業への移行により、従来の介護予防サービスに加えて、地域独自の多様なサービスが利用できるようになりました。例えば、住民ボランティアによる生活支援サービスや、NPO法人が提供する通いの場など、従来の介護保険サービスよりも柔軟で身近なサービスが増えています。
これは選択肢が増えるという意味ではメリットですが、一方で「どのサービスを選べば良いのか」という新たな悩みも生まれています。お住まいの地域包括支援センターに相談することで、あなたの状態や生活スタイルに最適なサービスを見つけることができます。
費用負担の変更可能性
所得に応じた負担割合の見直しにより、年金収入が一定額を超える方は負担が増加する可能性があります。具体的には、単身世帯で年金収入が280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合、2割負担となる可能性があります。さらに高所得の方は3割負担になることもあります。
ただし、高額介護サービス費制度により、月々の自己負担には上限が設けられています。世帯の所得状況に応じて、月額15,000円から44,400円の範囲で上限が設定されているため、極端に負担が増えることは防がれています。
ケアプランの見直しが必要なケース
制度改正に伴い、利用できるサービスの種類や内容が変わる場合があります。そのため、現在のケアプランが最適でなくなる可能性もあります。定期的なケアプランの見直しを担当のケアマネジャーと行うことで、常に最新の制度を活用した最適なサービスを受けることができます。
特に、総合事業のサービスを組み合わせることで、従来よりも効果的な介護予防や、費用の抑制が可能になることもあります。遠慮せずに「もっと良いサービスはないか」「費用を抑える方法はないか」とケアマネジャーに相談してみましょう。
2026年以降の制度改正予定と準備すべきこと
介護保険制度は今後も継続的に見直されていきます。2026年度には次回の大規模な改正が予定されており、要支援認定者にとっても重要な変更が含まれる可能性があります。
現在議論されている主なテーマには、ケアプランの有料化や軽度者向けサービスの見直しなどがあります。特に要支援者向けのサービスについては、より効率的で効果的な提供方法を目指して、さらなる見直しが検討されています。
今から準備できることとして、まずお住まいの自治体の総合事業の内容を確認しておくことをお勧めします。自治体によって提供されるサービスは大きく異なるため、早めに情報を集めておくことで、制度変更時にもスムーズに対応できます。
また、介護予防の取り組みを強化することも重要です。体操教室への参加や、地域のサロン活動への参加など、積極的に介護予防に取り組むことで、要支援の状態を維持・改善できる可能性が高まります。制度がどう変わっても、ご自身の健康状態が良ければ、サービスへの依存度を下げることができます。
介護保険改正と要支援に関する疑問解決
要支援から要介護に変わることはありますか
はい、要支援の方が要介護に変わることはあります。定期的な認定更新の際に、心身の状態が変化していれば、要介護認定を受ける可能性があります。逆に、積極的な介護予防の取り組みにより、要支援2から要支援1へ、あるいは非該当(自立)に改善するケースもあります。大切なのは定期的な状態評価と適切なサービスの利用です。
制度改正でサービスが使えなくなることはありますか
基本的に、すでに利用しているサービスが突然使えなくなることはありません。ただし、提供方法や事業者が変わる可能性はあります。例えば、介護予防訪問介護が総合事業のサービスに移行した場合でも、同様のサービスは継続して受けられますが、提供する事業者や細かい内容が変わることがあります。変更がある場合は、事前にケアマネジャーから説明がありますので、不安なことがあれば遠慮なく質問しましょう。
要支援でも施設入所はできますか
要支援認定では、原則として特別養護老人ホームなどの介護施設への入所はできません。ただし、軽費老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの施設は利用可能です。これらの施設では、必要に応じて外部の介護サービスを利用しながら生活することができます。また、状態が変化して要介護認定を受ければ、介護施設への入所も選択肢に入ります。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
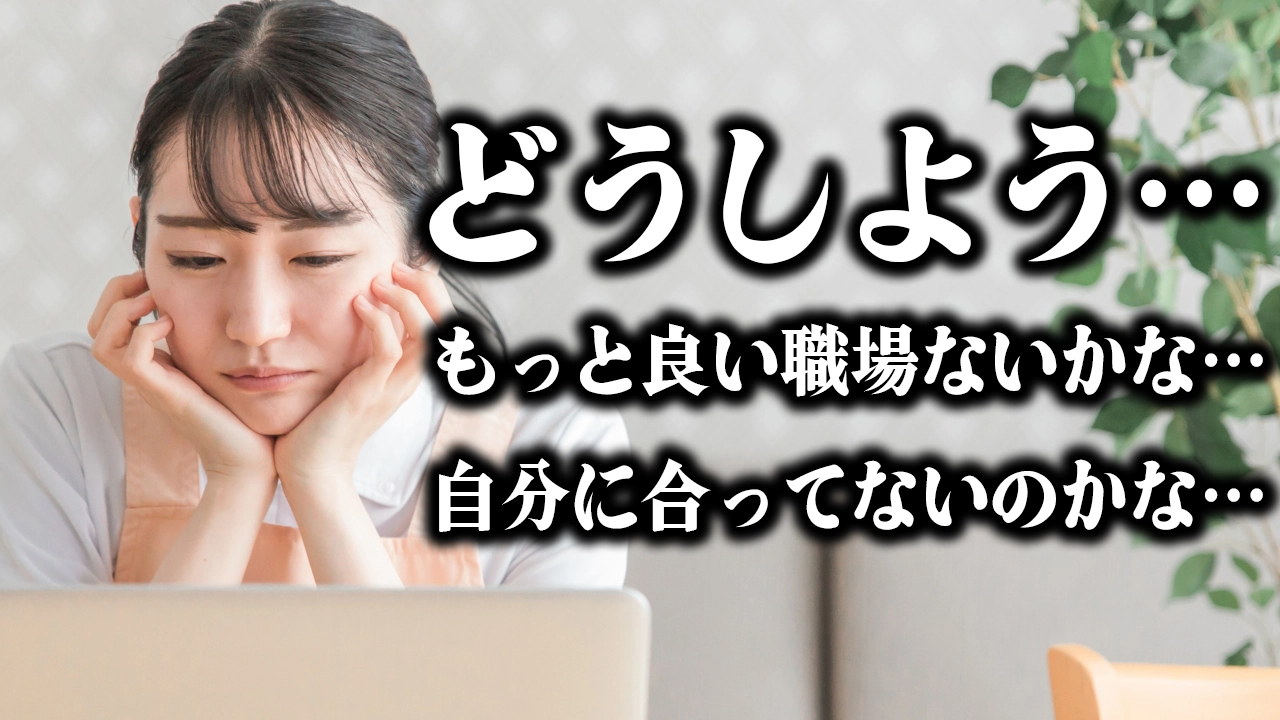
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ
介護保険制度の改正は複雑に見えますが、要支援認定を受けている方にとっての本質は「より効果的な介護予防と自立支援」を目指した変化です。総合事業の充実により地域に根ざしたサービスが増え、所得に応じた負担の適正化により制度の持続可能性が高まっています。
今すぐできる対応として、お住まいの地域包括支援センターに相談し、最新のサービス情報を入手すること、そしてご自身の負担割合を確認することをお勧めします。また、積極的な介護予防活動への参加は、制度改正の影響を最小限に抑える最も確実な方法です。
制度は変わっても、あなたらしい生活を続けるための支援体制は整っています。わからないことがあれば、遠慮なく専門家に相談し、制度を上手に活用していきましょう。




コメント