着替えに時間がかかったり、介助をされる方が痛がったり…。介護での着替え(更衣介助)は、毎日のことだからこそ「もっとスムーズにできないかな?」と悩んでいる方が多いのではないでしょうか。特に、初めて介護に直面した方は、どこから手をつければいいか分からず戸惑うこともありますよね。実は、ちょっとしたコツや知識があるだけで、驚くほど着替えが楽になり、介助する側もされる側もストレスがぐっと減るんです。この記事では、私が現場で見てきた経験と、専門家から学んだ知識をもとに、介護の着替えに関する「知られざる新常識」を5つ厳選してご紹介します。
介助が劇的に楽になる!介護服の選び方3つの秘訣

介護のイメージ
介護の着替えをスムーズにするには、まず「どんな服を選ぶか」が何よりも重要です。適切な介護服は、介助者の負担を減らすだけでなく、着る方の尊厳を守り、自立を促すことにも繋がります。しかし、世の中には様々な介護服があり、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。ここでは、私が介護のプロとして強くお勧めする、介護服選びの3つの秘訣をお伝えします。
秘訣1開閉機能に着目する「全開・半開」の使い分け
介護服を選ぶ際、まずチェックしてほしいのが「開閉機能」です。単に前開きになっているだけでなく、マジックテープやスナップボタンで簡単に着脱できるものがおすすめです。さらに重要なのは、全身が完全に開く「全開タイプ」と、胸元や肩だけが開く「半開タイプ」を使い分けることです。寝たきりの方や、着替えの際に体を動かすのが難しい方には、全開タイプが圧倒的に便利です。一方で、座って着替えができる方や、上着だけを着脱する際には、半開タイプでも十分対応できます。この使い分けを意識するだけで、着替えにかかる時間が劇的に変わります。
秘訣2素材は「伸縮性」と「滑りやすさ」が命
次に、服の素材です。一見すると地味なポイントに思えますが、実は介助のしやすさを大きく左右します。まず、伸縮性が高い素材を選びましょう。身体の動きに合わせて伸び縮みしてくれるので、介助者が無理に引っ張ったり、着る方が窮屈な思いをしたりすることがなくなります。さらに注目したいのが「滑りやすさ」です。特にフリース素材のような摩擦が大きい服は、着替えの際に身体がひっかかり、介助が非常に困難になることがあります。サラッとした肌触りのポリエステルや綿混合素材など、滑りの良い生地を選ぶことで、介助者の負担を軽減できます。
秘訣3デザインは「普段着」感覚で「明るい色」を選ぶ
介護服と聞くと、地味なデザインを想像するかもしれません。しかし、最近は機能性とデザイン性を両立したものが増えています。「普段着」感覚で着られるデザインや、明るい色を選ぶことは、着る方の気持ちを前向きにさせる上で非常に大切です。例えば、かわいらしい花柄や、落ち着いたストライプ柄など、本人の好みに合わせたデザインを選ぶことで、着替えること自体が楽しみになります。気分が沈みがちな時期だからこそ、色や柄の持つ力を最大限に活用しましょう。
知って差がつく!介護の着替え介助9割が間違える5つの新常識
介護の着替えには、多くの人が知らない「新常識」があります。これらのポイントを押さえるだけで、介助がスムーズになるだけでなく、着る方の安心感と自立心を高めることができます。
新常識1声かけは「着替え」ではなく「〇〇しましょう」と具体的に
介助の第一歩は声かけです。多くの方が「着替えしましょう」と声をかけますが、これでは漠然としていて、着る方が何をすればいいのか戸惑ってしまうことがあります。より効果的なのは、「これから上着を脱ぎますね」「右腕から袖を通しますよ」のように、具体的に何をしようとしているのかを伝えることです。これにより、着る方は介助を受ける心の準備ができ、無用な不安を軽減できます。
新常識2着脱の順番は「脱健着患」が基本!その理由とは?
介護の着替えには、有名な鉄則があります。それが「脱健着患(だっけんちゃっかん)」です。これは、「服を脱ぐときは健康な方(動かせる方)の腕から、服を着るときは麻痺している方(動かしにくい方)の腕から」という介助の順番を表す言葉です。この順番を守ることで、麻痺した部分に負担をかけることなく、スムーズに着替えができます。このシンプルなルールを知っているか知らないかで、介助の負担は大きく変わります。
新常識3寝たまま着替えさせる「介助方法」の裏技
寝たきりの方の着替えは、介助の中でも特に大変な作業です。しかし、実は「裏技」があります。寝たままの状態で着替えをさせるには、まず上半身を少し起こすことが重要です。介助者は、片手で着る方の肩を支え、もう片方の手で服を脱がせたり着せたりします。このとき、服を小さくたたんで背中に滑り込ませるようにすると、身体を大きく動かすことなく着替えが可能です。無理に身体を持ち上げようとせず、服を上手に扱うことがポイントです。
新常識4着替え介助は「自立支援」の視点から考える
着替えをすべて介助者がやってしまうのではなく、「できることは本人にやってもらう」という意識を持つことが大切です。例えば、自分でボタンを留められる方であれば、その部分は任せてみましょう。たとえ時間がかかっても、本人の「できる」をサポートすることは、自尊心を保ち、リハビリにも繋がります。介助者は「手伝う人」ではなく「支える人」という視点を持つことが、着替え介助の最も重要な心構えです。
新常識5環境設定が成否を分ける「室温・プライバシー」の配慮
着替えの際の環境設定は、快適さを左右する重要な要素です。まず、室温を適切に保ちましょう。着替え中は体が冷えやすいので、暖房を少し高めに設定したり、夏場でも冷房が直接当たらないようにしたりするなど、細やかな配慮が大切です。また、着替えは非常にプライベートな行為です。カーテンを閉めたり、ドアをノックしてから入るなど、プライバシーに最大限配慮することで、着る方の安心感は大きく高まります。
介護服の着替えに関する疑問解決Q&A
介護の着替えについて、よくある疑問に専門的な視点からお答えします。
Q1片麻痺の場合、どんな介護服を選べばいいですか?
片麻痺がある方の場合、特に「全開タイプ」の服がおすすめです。ズボンも脇の部分が完全に開くタイプや、足首から太ももまでファスナーで開くタイプなどがあります。これらの服は、麻痺がある方でも介助者が楽に着脱させることができ、着る方の負担も減らせます。
Q2着替えを嫌がる場合はどうすればいいですか?
着替えを嫌がる背景には、様々な理由が考えられます。例えば、痛みがある、恥ずかしい、介助者への不信感、または認知機能の低下によるものです。まずは、なぜ嫌がるのかを優しく探ることが大切です。痛みがある場合は、無理に着替えさせず、医療従事者に相談しましょう。また、好きな音楽をかけたり、楽しい会話をしながら着替えをするなど、雰囲気を変える工夫も有効です。
今すぐ介護の悩みを解決したい!どうしたらいい?

「親族の介護、もう待てない状況になっていませんか?」
介護は突然やってきます。「まだ大丈夫」と思っていても、転倒や急な体調変化で一気に現実となることも。
そんな時、慌てて施設を決めて後悔しないために。
もちろん、今介護で悩んでいる人であってもどの施設であればすぐに入れるのかを事前に情報収集する必要があります。
そんなとき「みんなの介護」なら、業界最大手の安心感と51,000件という圧倒的な選択肢で、あなたがどんな状況でもベストな施設が見つかります。
⭐ 掲載施設数No.1の実績
⭐ 経験豊富な相談員が24時間サポート
⭐ 見学予約から入居まで完全無料でフォロー
「あの時、もっと調べておけば良かった」
そんな後悔をしないために、今すぐ行動を。
複数施設の資料を取り寄せて、ご家族で安心できる選択をしませんか?
▼無料資料請求はこちら▼
資料請求はこちら
![]()
たった一度の着替えから変わる未来行動を促すまとめ
介護の着替えは、日々の生活の中で何度も繰り返される大切なケアです。この記事でご紹介した「介護服の選び方3つの秘訣」や「9割が間違える5つの新常識」は、一見すると些細なことかもしれません。しかし、これらの知識と実践が、介助する側の負担を軽減し、される側の尊厳と自立心を守ることに繋がります。
大切なのは、「着替え=単なる作業」ではなく、「着替え=コミュニケーションの場」と捉えることです。温かい声かけ、ちょっとした工夫、そして相手の気持ちに寄り添う心。これらが組み合わさることで、着替えの時間が互いにとって心地よい時間へと変わります。
この記事を読んだあなたが、今日から一つでも新しい知識を実践し、日々の介護がより良いものになることを願っています。



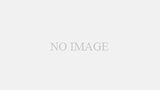
コメント