介護保険制度は常に変化し続けています。特に令和6年度の改正では、介護予防・日常生活支援総合事業に大きな変更が加えられました。「また制度が変わるの?」「今回の改正で何が変わったの?」と戸惑っている介護事業者の方や、ケアマネジャーの皆さんも多いのではないでしょうか。実は、この改正を正しく理解していないと、報酬請求でミスをしたり、利用者に適切なサービスを提供できなくなったりする可能性があります。この記事では、R6年度介護保険改正における総合事業の変更点を、初心者の方でも理解できるよう丁寧に解説していきます。
そもそも総合事業とは?基本から理解する

介護のイメージ
介護予防・日常生活支援総合事業は、平成27年度の介護保険法改正により創設された仕組みです。従来は全国一律の基準で提供されていた介護予防サービスが、市町村が地域の実情に応じて柔軟に提供できるようになりました。
この総合事業は大きく2つの柱で構成されています。1つ目は介護予防・生活支援サービス事業で、要支援者や基本チェックリストに該当する方を対象に、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスを提供します。2つ目は一般介護予防事業で、すべての高齢者を対象とした予防活動を展開しています。
従来の介護予防訪問介護や介護予防通所介護は、この総合事業に移行したため、サービスの提供方法や報酬体系が大きく変化しました。地域によって独自のサービスメニューを設定できるようになったことで、より地域のニーズに合ったサービス提供が可能になったのです。
R6年度改正の目玉!処遇改善加算の一本化とは
令和6年6月の改正で最も注目すべきは、処遇改善加算の一本化です。これまで複雑だった加算体系が整理され、従前相当サービスと訪問型サービスA1において、処遇改善加算がシンプルになりました。
この一本化により、事業所の事務負担が大幅に軽減されました。従来は複数の加算区分を理解し、それぞれに応じた書類を準備する必要がありましたが、新しい仕組みでは申請手続きが簡素化されています。介護職員の処遇改善を図りながら、事業所の負担を減らすという、両方の目的を達成する画期的な改正といえるでしょう。
また、通所型サービスA7については、送迎未実施減算に月額報酬が新たに設定されました。送迎を実施しない場合の報酬体系が明確になり、サービス提供の実態に即した報酬算定が可能になったのです。
業務継続計画(BCP)未策定減算の新設
令和7年4月からは、業務継続計画未策定減算が新たに適用されることになりました。これは従前相当訪問型サービス、訪問型サービスA1、そして介護予防ケアマネジメント費に影響を与える重要な変更です。
業務継続計画とは、災害や感染症などの緊急事態が発生した際にも、介護サービスを継続的に提供できるようにするための計画です。新型コロナウイルス感染症の経験から、その重要性が改めて認識され、今回の改正で義務化の流れが強化されました。
未策定の場合は報酬が減算されるため、事業所は早急にBCPを整備する必要があります。ただし、いきなり完璧な計画を作る必要はありません。まずは基本的な内容から始め、定期的に見直しながら実効性のある計画に育てていくことが大切です。
サービスコード表と単位数マスタの更新ポイント
改正に伴い、サービスコード表と単位数マスタも更新されています。令和7年4月施行版では、業務継続計画未策定減算に対応した新しいコードが追加されました。
請求業務を担当する方は、必ず最新のサービスコード表を確認してください。古いコードを使用すると、請求エラーが発生したり、正しい報酬を受け取れなかったりする可能性があります。特に令和6年度中は、6月と4月に2回の大きな更新がありましたので、どの時点のコードを使用すべきか注意が必要です。
CSV形式の単位数マスタも提供されているため、事業所で使用している請求システムに取り込むことで、効率的に対応できます。システムベンダーと連携しながら、スムーズな移行を進めましょう。
前橋市の事例から学ぶ実務対応
前橋市では平成29年4月から総合事業を実施しており、その後も継続的に制度を改善してきました。前橋市の実施要綱は、他の自治体の参考にもなる充実した内容となっています。
特筆すべきは、給付管理連絡票の前橋市独自様式です。配食サービスなど指定以外の利用サービスについても記載できるよう工夫されており、利用者の生活全体を把握しやすい設計になっています。これにより、ケアマネジャーは利用者の状況をより包括的に管理できるようになりました。
また、月額包括報酬の日割り請求については、具体的な事例を交えた詳細な説明資料が提供されています。利用者がサービスを開始・終了する際の請求方法は複雑になりがちですが、こうした資料を活用することで、正確な請求が可能になります。
臨時的な取扱いと新型コロナ対応の変遷
新型コロナウイルス感染症の流行期には、報酬算定の臨時的な取扱いが実施されました。令和5年5月8日の感染症法上の位置づけ変更に伴い、これらの特例措置も段階的に見直されています。
訪問型・通所型サービスにおいて、感染症対策を講じながらサービスを継続した事業所に対する加算措置や、人員基準の緩和などが行われました。現在は通常の体制に戻りつつありますが、この経験は今後のBCP策定においても重要な教訓となります。
感染症対応で学んだ柔軟なサービス提供の工夫や、ICTを活用した遠隔でのケアマネジメントなど、今後も活用できる取り組みが数多く生まれました。これらを日常の業務に取り入れることで、より質の高いサービス提供が可能になるでしょう。
介護予防ケアマネジメントの実務ポイント
総合事業における介護予防ケアマネジメントは、利用者の自立支援を目指す上で非常に重要な役割を担っています。従来の介護予防支援とは異なる部分もあるため、正しい理解が必要です。
ケアマネジメントには3つの類型があります。ケアマネジメントAは原則的な形で、アセスメントからモニタリングまで一連のプロセスを実施します。ケアマネジメントBは簡略化された形で、サービス内容が定型的な場合に適用されます。ケアマネジメントCは初回のみで、その後は利用者の自己管理に委ねる形です。
利用者の状態や目標に応じて適切な類型を選択することで、効果的な支援と効率的な業務運営の両立が可能になります。手引き書には詳細な書式例が掲載されているため、実務の参考にしてください。
r6介護保険改正総合事業に関する疑問解決
今回の改正で事業所が最優先で対応すべきことは何ですか?
最優先で対応すべきは業務継続計画の策定です。令和7年4月から未策定の場合は減算が適用されるため、時間的な余裕はあまりありません。まずは基本的な災害対応と感染症対応の計画を作成し、その後、定期的な訓練と見直しを通じて実効性を高めていきましょう。また、処遇改善加算の一本化に伴う届出書類の更新も早めに済ませておくことをお勧めします。
処遇改善加算の一本化で報酬額は変わりますか?
基本的な報酬額に大きな変更はありませんが、加算の申請手続きが簡素化されることで、事務負担が軽減されます。これまで複数の加算を組み合わせて申請していた事業所は、手続きがシンプルになることでミスのリスクも減少します。ただし、加算を適切に取得するための要件は引き続き満たす必要がありますので、職員の資質向上や待遇改善の取り組みは継続してください。
前橋市以外の自治体でも同じように対応すれば良いですか?
総合事業は市町村ごとに実施要綱が定められているため、必ずお住まいの自治体の要綱を確認してください。前橋市の事例は参考になりますが、報酬単価やサービス類型、基準などは自治体によって異なります。不明点があれば、管轄する市町村の介護保険担当課に直接問い合わせることをお勧めします。多くの自治体では事業者向けの説明会も開催していますので、積極的に参加しましょう。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
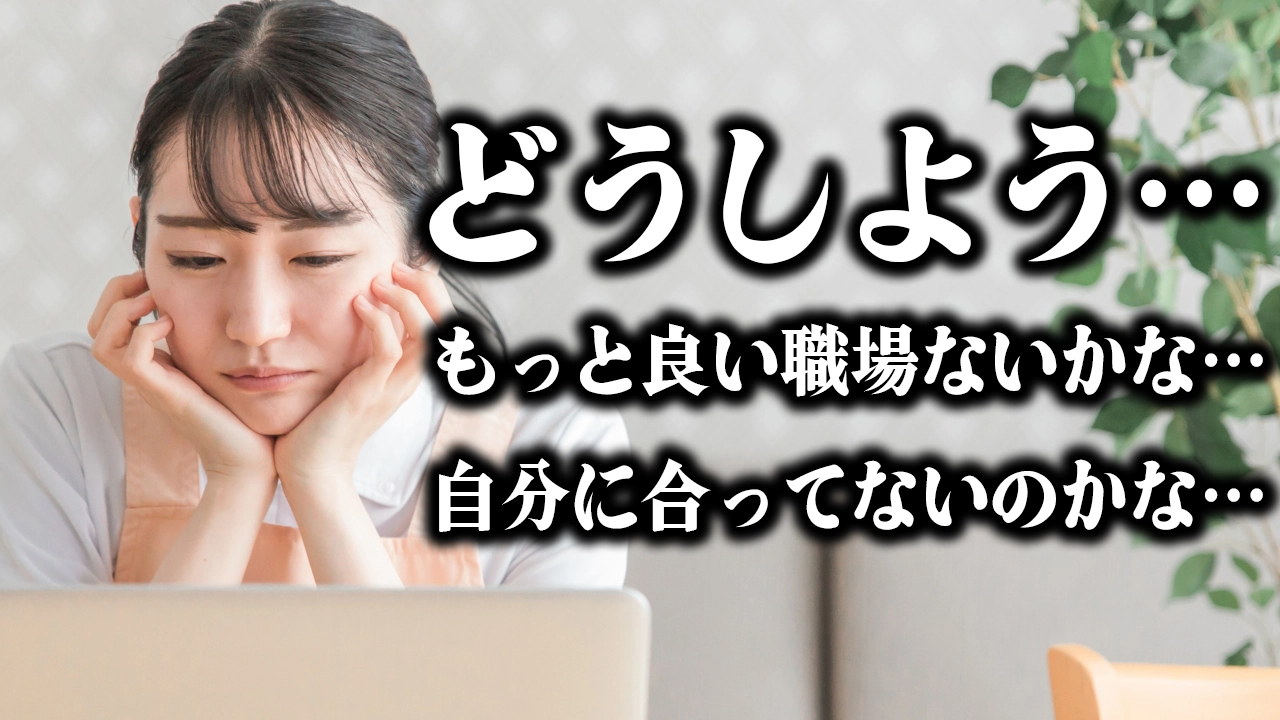
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ改正を味方につけて質の高いサービスを
R6年度の介護保険改正における総合事業の変更は、一見複雑に見えますが、その本質は介護サービスの質を向上させ、持続可能な制度を構築することにあります。処遇改善加算の一本化は事務負担を軽減し、BCPの策定は緊急時でも安定したサービス提供を可能にします。
今回の改正を単なる義務として捉えるのではなく、事業所の体制を見直し、サービスの質を向上させる機会として前向きに取り組んでください。最新のサービスコード表を確認し、必要な届出を期限内に行い、利用者により良いサービスを提供できる体制を整えましょう。制度は変わり続けますが、私たち介護従事者の目指す方向性は変わりません。それは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく生活し続けられるよう支援することです。この改正を味方につけて、さらに質の高いサービス提供を目指していきましょう。




コメント