2024年度の介護保険改正によって、訪問看護の現場は大きな転換期を迎えています。「また新しいルールが増えた」「うちの事業所は大丈夫だろうか」そんな不安を抱えている管理者の方も多いのではないでしょうか。実は、この改正には単なる規制強化だけでなく、サービスの質を根本から見直すチャンスが隠されているのです。
今回の改正で導入された新しい減算ルールは、一見すると事業所にとって厳しく感じるかもしれません。しかし、これらは利用者の安全と尊厳を守り、持続可能な訪問看護サービスを実現するための重要な指針なのです。この記事では、介護保険改正が訪問看護に与える影響を徹底解説し、あなたの事業所が改正を味方につけて成長するための実践的な対策をご紹介します。
2024年度介護保険改正が訪問看護にもたらした3つの大きな変化

介護のイメージ
今回の介護保険改正は、単なる報酬の見直しにとどまらず、訪問看護の在り方そのものを問い直す内容となっています。厚生労働省が目指したのは、災害や感染症などの危機的状況下でも安定したサービスを提供できる強靭な体制づくりです。
まず注目すべきは、看護の専門性を重視する方向性が明確に示されたことです。リハビリテーション専門職の役割は重要ですが、訪問看護はあくまで看護職が主体となって利用者の生活全体を支えるサービスであるという原点に立ち返る改正となりました。これは、医療ニーズの高い利用者が増加する中で、看護の視点に基づいた総合的なアセスメントと支援の重要性が再認識された結果といえるでしょう。
次に、事業継続性の確保が義務化されました。新型コロナウイルス感染症の経験から、どんな状況下でも利用者に必要なサービスを届け続ける体制の構築が急務となったのです。そして第三に、利用者の尊厳と権利を守る仕組みの強化が図られました。高齢者虐待防止への取り組みは、単なる形式的な対応ではなく、組織文化として根付かせることが求められています。
絶対に押さえるべき5つの重要改正ポイントと実務への影響
ポイント1リハビリ専門職の訪問回数超過減算の新設
2024年度改正で最も大きな衝撃を与えたのが、この減算の新設です。前年度において理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問回数が看護職員の訪問回数を超過した場合、訪問1回につき8単位が減算されることになりました。
この改正の背景には、一部の事業所でリハビリ職の訪問に偏重し、本来の看護サービスが十分に提供されていないケースが見られたという実態があります。訪問看護は、医療処置だけでなく、利用者の生活全体を見渡して健康管理や療養指導を行う総合的なサービスです。リハビリテーションはその一部として位置づけられるべきであり、看護とリハビリのバランスの取れた提供体制を構築することが求められています。
実務への影響として、年間の訪問計画を戦略的に立てる必要性が高まりました。特に年度末が近づいた時点で回数の偏りに気づいても、もはや調整が困難です。月次で訪問実績を確認し、必要に応じて計画を修正する仕組みづくりが不可欠となります。
ポイント2業務継続計画(BCP)未策定減算の義務化
2025年4月1日以降、感染症または災害に関する業務継続計画が未策定の場合、基本報酬から1%が減算されます。これは金額的にも大きな影響があり、月間100万円の報酬がある事業所なら年間12万円の減収となる計算です。
BCPは単なる書類作成ではありません。実際に災害や感染症が発生した際、どのように優先順位をつけて利用者にサービスを提供するのか、スタッフの安全をどう確保するのか、代替手段はどうするのかといった実効性のある計画である必要があります。厚生労働省が提供するひな形を参考にしながら、自事業所の実情に合わせたカスタマイズが重要です。
さらに、策定だけでなく定期的な研修と訓練の実施も義務付けられています。年に一度はBCPに基づいたシミュレーション訓練を行い、計画の実効性を検証しましょう。訓練を通じて発見された課題は、計画の見直しに反映させることで、真に機能するBCPへと進化させることができます。
ポイント3高齢者虐待防止措置未実施減算の導入
利用者の尊厳を守るため、高齢者虐待防止に関する4つの措置がすべて実施されていない場合、基本報酬から1%が減算されます。この4つの措置とは、虐待防止委員会の設置、指針の整備、研修の実施、そして担当者の配置です。
虐待は身体的なものだけではありません。心理的虐待、介護や世話の放棄・放任、経済的虐待など、さまざまな形態があります。特に訪問看護の現場では、利用者の自宅という密室での一対一のケアとなるため、組織として虐待を未然に防ぐ仕組みが極めて重要です。
効果的な虐待防止策として、事例検討会の定期開催が挙げられます。「このケアは適切だろうか」「利用者の意思を尊重できているだろうか」といった問いを職員全員で共有し、ケアの質を高める文化を醸成することが大切です。また、スタッフが困難な状況に直面したときに相談できる体制を整えることも、虐待の芽を摘むことにつながります。
ポイント4同一建物減算の適用範囲の明確化
集合住宅や高齢者向け住宅での訪問看護には、以前から同一建物減算が適用されていましたが、今回の改正で適用範囲がより明確になりました。同一敷地内の別棟であっても、一体的に利用されている場合は減算対象となるケースがあります。
減算率は利用者数に応じて変動し、同一日に3人以上訪問する場合は10%、10人以上の場合は15%となります。この減算は避けられないケースも多いですが、訪問スケジュールの最適化によって業務効率を高め、減算の影響を相殺することは可能です。
具体的には、同一建物内の利用者をまとめて訪問する時間帯を設定し、移動時間を最小限に抑える工夫が有効です。また、ケアマネジャーや施設管理者との密な連携により、利用者のニーズに応じた効率的なサービス提供計画を立てることが重要となります。
ポイント5准看護師による訪問減算の継続
准看護師が訪問看護を提供した場合、所定単位数から10%が減算されるルールは継続されています。これは看護師と准看護師の資格や業務範囲の違いを報酬に反映させたものです。
人材確保が困難な中、准看護師の活用は重要な選択肢の一つですが、経営面でのバランスを考慮する必要があります。准看護師が担当するケースと看護師が担当するケースを適切に振り分け、准看護師には看護師の指導のもとで段階的にスキルアップを図る育成計画を立てることが、長期的な事業所の成長につながります。
今すぐ実践できる!減算回避と質向上を両立させる5つの対策
対策1多職種カンファレンスの定例化で訪問バランスを最適化
リハビリ専門職の訪問回数超過減算を回避するには、月次での訪問実績のモニタリングと、多職種による定期的なカンファレンスが効果的です。看護職とリハビリ職が利用者の状態や目標を共有し、それぞれの専門性を活かした役割分担を明確にすることで、自然とバランスの取れた訪問計画が実現します。
具体的には、利用者ごとに「今月は看護の視点からのアセスメントを強化する必要がある」「リハビリの進捗が良好なので、自主トレーニングの指導にシフトする」といった判断を、チームで協議しながら進めることが重要です。これにより、減算回避だけでなく、利用者にとって最適なサービス提供が可能となります。
対策2BCP策定の3ステップアプローチ
BCPの策定は、以下の3つのステップで進めると効率的です。第一ステップは、自事業所が直面する可能性のあるリスクの洗い出しです。地域の災害履歴、感染症の流行パターン、事業所の立地条件などを考慮して、優先的に対策すべきリスクを特定します。
第二ステップは、厚生労働省のひな形をベースに、自事業所の実情に合わせた具体的な行動計画の作成です。連絡体制、優先順位の決定方法、代替手段、必要な備品リストなど、実際に使える内容にすることが重要です。
第三ステップは、定期的な訓練と見直しです。年に一度はシミュレーション訓練を実施し、計画の実効性を検証しましょう。訓練で見つかった課題は、すぐに計画に反映させることで、真に役立つBCPへと進化していきます。
対策3虐待防止を組織文化として定着させる仕組みづくり
虐待防止措置は、形式的な委員会や研修の実施だけでは不十分です。日常的にケアの質を振り返る文化を組織に根付かせることが本質的な対策となります。
効果的な方法として、週次の短時間ミーティングで「今週気になったケース」を共有する時間を設けることをお勧めします。難しいケースや判断に迷った場面を職員全員で共有し、「より良いアプローチはなかっただろうか」と建設的に議論することで、チーム全体のケアの質が向上します。
また、ストレスチェックの定期実施と、スタッフが気軽に相談できる窓口の設置も重要です。虐待は追い詰められた状況で発生することが多いため、スタッフの心身の健康を守ることが、結果として利用者の安全にもつながるのです。
対策4デジタルツールを活用した記録管理の徹底
すべての減算対策の基礎となるのが、正確で詳細な記録です。訪問看護記録システムやスケジュール管理アプリなどのデジタルツールを活用することで、記録の質を高めつつ業務効率も向上させることができます。
記録には、サービスの内容だけでなく、その判断根拠や利用者の反応、今後の方針なども具体的に記載しましょう。「バイタルサイン測定実施」だけでなく、「血圧がやや高めのため、水分摂取と休息を指導。次回訪問時に再評価予定」といった形で、看護の専門性が見える記録を心がけることが重要です。
対策5定期的な内部監査とセルフチェック体制の構築
減算のリスクを事前に発見するには、定期的な内部監査が効果的です。月次または四半期ごとに、減算要件に該当していないかをチェックする仕組みを作りましょう。特に、リハビリ職の訪問回数、BCP関連の研修実施記録、虐待防止委員会の開催状況などは、重点的に確認すべき項目です。
また、各スタッフが日常的に自己チェックできるチェックリストを作成し、定期的に見直す習慣をつけることも有効です。これにより、問題を早期に発見し、迅速に対応することが可能となります。
介護保険改正と訪問看護に関する疑問解決
リハビリ職の訪問回数は月単位で管理すべきですか、年単位ですか?
リハビリ専門職の訪問回数超過減算は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績に基づいて判断されます。そのため、年度単位での管理が必須です。ただし、年度末に気づいても調整が困難なため、月次でのモニタリングと四半期ごとの見直しを行い、年間を通じてバランスを保つことが重要です。具体的には、看護職とリハビリ職の訪問回数を毎月集計し、偏りがないかを確認する習慣をつけましょう。
BCPは感染症と災害の両方を策定する必要がありますか?
はい、理想的には感染症と災害の両方について策定することが推奨されます。2025年4月1日以降は、いずれか一方でも未策定の場合に減算が適用されます。それぞれのリスクは性質が異なるため、別々の計画として策定した方が実効性が高まります。ただし、共通する部分(連絡体制、意思決定プロセスなど)については統合して記載することで、策定の負担を軽減できます。厚生労働省が提供するひな形を活用しながら、自事業所の実情に合わせた計画を作成しましょう。
同一建物減算の対象となる「同一敷地内」の判断基準は?
同一敷地内とは、その建物が所在する土地や隣接する土地のうち、一体的に利用されている範囲を指します。例えば、同じ敷地内に複数の棟がある集合住宅や、道路を隔てていても専用通路で接続されている建物などが該当します。判断が難しいケースでは、必ず指定権者(都道府県や市町村)に事前確認することをお勧めします。誤った判断による算定ミスは、後の返還請求につながる可能性があるため、慎重に対応しましょう。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
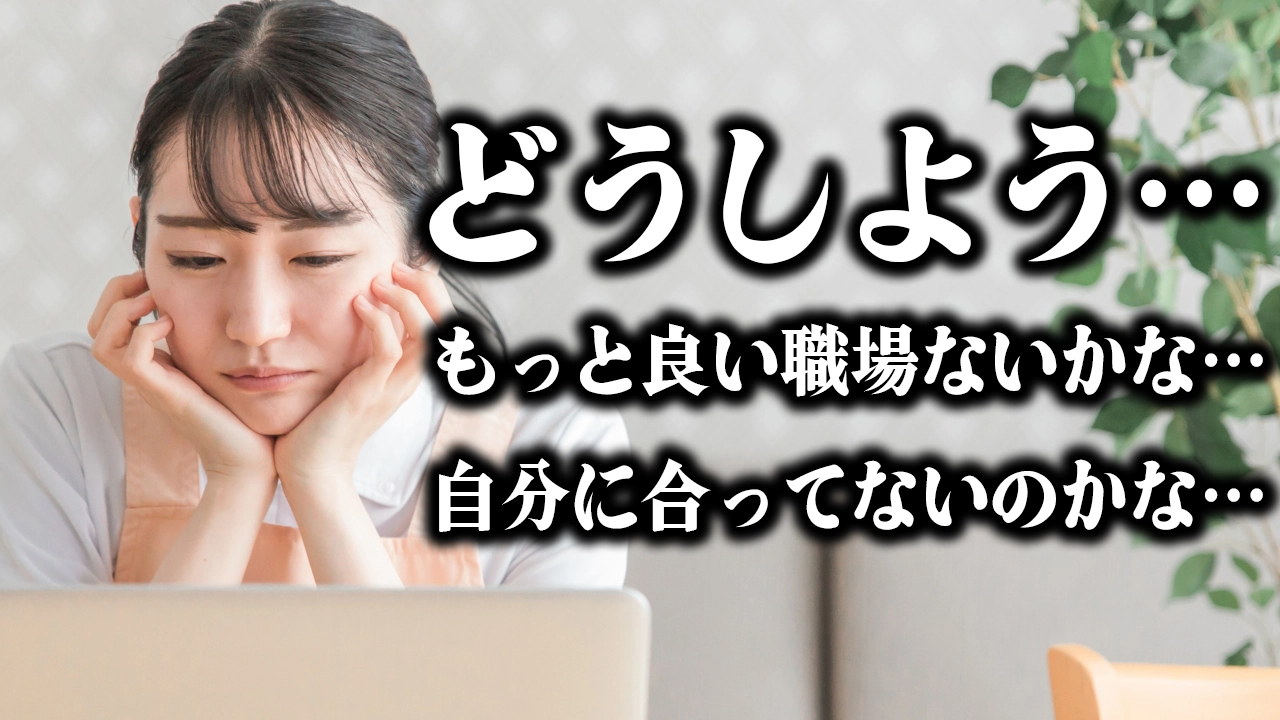
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ介護保険改正を成長の機会として捉えよう
2024年度の介護保険改正は、確かに訪問看護事業所にとって新たな課題をもたらしました。しかし、視点を変えれば、これはサービスの質を根本から見直し、より強固な経営基盤を構築する絶好の機会でもあります。
減算を恐れるあまり萎縮するのではなく、改正の趣旨を正しく理解し、利用者にとって本当に価値あるサービスとは何かを問い直すことが大切です。看護とリハビリのバランスの取れた提供、災害時にも継続できる体制づくり、利用者の尊厳を守る組織文化の醸成。これらはすべて、持続可能で質の高い訪問看護サービスを実現するための本質的な要素なのです。
今日から、この記事で紹介した具体的な対策を一つずつ実践してみてください。多職種カンファレンスの定例化、BCPの策定、記録管理の徹底。小さな一歩の積み重ねが、あなたの事業所を改正に強い、そして利用者から選ばれる訪問看護ステーションへと成長させていくはずです。改正を味方につけて、共に質の高いサービスを提供していきましょう。




コメント