2024年度の介護報酬改定により、訪問看護ステーションの経営環境が大きく変わりました。特に理学療法士等による訪問に対する新たな減算ルールは、多くの事業所に深刻な影響を与えています。「今月の収益が予想より大幅に減った」「減算対象になっているけど、どう対応すればいいのか分からない」そんな悩みを抱えていませんか。実は、この改定には厚生労働省の明確な意図があり、それを理解することで適切な対策を講じることができます。本記事では、減算ルールの詳細から具体的な回避戦略、さらには新設された加算の活用法まで、訪問看護ステーションの経営を守るための実践的な情報をお届けします。
2024年度介護報酬改定が訪問看護に与える本質的な影響

介護のイメージ
今回の介護報酬改定は、単なる報酬単価の変更ではありません。厚生労働省は、訪問看護ステーションの機能分化を明確に促しています。背景には、一部の事業所が軽度な利用者へのリハビリテーションサービスを中心に、平日日中のみの運営を行っている実態がありました。
改定の核心は、訪問看護本来の役割である24時間365日体制での医療ニーズの高い利用者へのサービス提供を評価する仕組みへの転換です。つまり、看護職員による訪問を中心としたステーションが評価され、理学療法士等の訪問に偏った事業所には厳しい環境となっています。
実際のデータを見ると、令和3年度の改定後、特に要支援者に対する訪問回数が減少傾向にあり、この流れは今後も続くと予想されます。訪問看護においてリハビリテーションを受けている利用者の介護度は、要介護2が22.2%で最も多く、次いで要介護5が16.2%と二極化しています。この事実は、訪問看護ステーションが多様な利用者層に対応する必要性を示しています。
新減算ルールの完全理解|あなたのステーションは対象?
8単位減算が適用される2つの条件
2024年度の改定で最も注目すべきは、理学療法士等が訪問した際に1回につき8単位が減算されるという新ルールです。この減算は、以下の2つのいずれかに該当する場合に適用されます。
第一の条件は、前年度の理学療法士等の訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合です。これは事業所全体での比較となるため、自事業所の訪問実績を正確に把握することが不可欠です。具体的には、居宅サービス計画書、訪問看護報告書、訪問看護記録書等を参照し、前年度の実績を集計する必要があります。
第二の条件は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算のいずれも算定していない場合です。これらの加算は、医療ニーズの高い利用者へのサービス提供体制を評価するものであり、少なくとも1つは算定していることが減算回避の鍵となります。
訪問回数の数え方が変更|計算ミスに要注意
従来、40分の訪問は2回分として算定していましたが、最新の解釈では大きく変わりました。理学療法士等が連続して訪問した場合、算定回数は複数でも訪問回数は1回としてカウントされます。
例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問した場合、算定回数は4回ですが、訪問回数は2回です。また、同日の午前に1回、午後に連続して2回訪問した場合、算定回数は3回でも訪問回数は2回となります。この計算方法を誤ると、減算対象かどうかの判断を間違える可能性があるため、記録管理の徹底が重要です。
介護予防訪問看護のさらなる減算強化
介護予防訪問看護では、状況がさらに厳しくなっています。12か月を超えて実施する場合、介護予防看護費の減算を算定している場合は1回につき月15単位のさらなる減算、算定していない場合でも1回につき5単位の減算が適用されます。要支援者へのサービス提供を行っている事業所は、特に注意が必要です。
減算を回避するための5つの実践戦略
戦略1看護職員の訪問比率を高める体制整備
最も直接的な対策は、看護職員による訪問回数を増やすことです。ただし、単に訪問回数を増やすだけでは人件費が増大し、かえって収益を圧迫します。効果的なアプローチは、看護職員とリハビリ職員の役割分担を明確にし、看護職員が担うべき医療ニーズの高い利用者を積極的に受け入れる体制を構築することです。
具体的には、医療依存度の高い利用者、ターミナルケアが必要な利用者、特別管理が必要な利用者などを優先的に受け入れることで、看護職員の訪問機会が自然と増加します。同時に、地域の医療機関との連携を強化し、退院支援から訪問看護への流れをスムーズにすることも重要です。
戦略23つの加算のうち最低1つを確実に算定する
緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算のいずれかを算定していれば、理学療法士等の訪問回数が看護職員を上回っていても8単位減算は回避できます。最も取り組みやすいのは緊急時訪問看護加算です。
この加算を算定するには、24時間連絡体制を確保し、利用者やその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制が必要です。また、緊急訪問が可能な体制を整え、利用者に対して文書で説明し同意を得ることが求められます。当番制やオンコール体制を整備することで、中小規模のステーションでも対応可能です。
戦略3利用者の適切なセグメンテーションとサービス設計
すべての利用者に同じようなサービスを提供するのではなく、利用者の状態に応じて最適なサービスを設計することが重要です。医療ニーズが高く、看護職員による専門的なケアが必要な利用者と、リハビリテーションが中心となる利用者を明確に分類し、それぞれに適したサービス提供体制を構築します。
リハビリテーションが中心の利用者については、訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業所との連携を検討することも一つの選択肢です。利用者にとって最適なサービスを提供することが、結果的に事業所の経営安定化にもつながります。
戦略4連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の活用
連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も、前年度の理学療法士等による訪問回数に含まれます。この制度を活用することで、看護職員による訪問機会を増やし、同時に利用者により手厚いサービスを提供することができます。
この制度は、要介護度が高く、頻回な訪問が必要な利用者に特に適しています。定期的な巡回訪問と随時の対応を組み合わせることで、利用者の在宅生活を総合的に支援できる体制が構築できます。
戦略5訪問スケジュールの最適化による生産性向上
減算を回避しながら収益を確保するには、限られたリソースで最大の効果を生み出す必要があります。訪問スケジュールを最適化し、移動時間の削減や訪問件数の増加を実現することで、減算の影響を最小限に抑えることができます。
効率的なルート設定、利用者の希望時間と職員の勤務シフトの最適なマッチング、チーム制やローテーション制の導入など、スケジュール管理の改善は多岐にわたります。デジタルツールを活用することで、人の手では困難だった複雑な条件を考慮したスケジューリングが可能になります。
新設・見直しされた加算の戦略的活用法
リハビリテーションマネジメント加算の強化ポイント
2024年度改定では、リハビリテーションマネジメント加算に新たな区分が追加されました。事業所の医師が利用者またはその家族に対して説明し、同意を得た場合、従来の加算に加えて270単位/月を算定できます。
この加算を算定するためには、多職種が共同してリハビリテーションの質を継続的に管理する体制が不可欠です。具体的には、3ヵ月に1回以上のリハビリテーション会議の開催、利用者の状態変化に応じた計画の見直し、ケアマネジャーや他サービス事業所への積極的な情報提供などが求められます。
医師の役割も重要です。リハビリテーションの目的に加え、開始前や実施中の留意事項、中止基準、利用者への負荷などについて、理学療法士等に対して明確な指示を行う必要があります。これらの指示内容は、記録として残すことが必須です。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の活用
認知症と医師が判断した利用者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれる場合、240単位/日を算定できます。算定は1週に2日が限度ですが、退院日または訪問開始日から3ヵ月以内という期間限定での集中的なアプローチが評価されます。
認知症の利用者に対するリハビリテーションは、身体機能の維持・向上だけでなく、認知機能の維持や生活リズムの確立にも効果があります。早期からの集中的な介入により、その後の在宅生活の質を大きく向上させることができます。
サービス提供体制強化加算で職員の質を評価
サービス提供体制強化加算は、事業所の人材育成体制と職員の定着状況を評価するものです。加算(Ⅰ)では勤続年数7年以上の職員が30%以上、加算(Ⅱ)では3年以上の職員が30%以上という要件があります。
この加算を算定するためには、すべての看護師等に対する個別の研修計画の作成と実施、月1回以上の情報共有会議の開催、年1回以上の健康診断の実施が必要です。単に加算を算定するだけでなく、これらの取り組みを通じて職員の質を高め、定着率を向上させることが、長期的な経営安定化につながります。
介護保険改正訪問看護に関する疑問解決
Q1減算対象かどうかをいつ判定すればよいですか?
減算対象の判定は、前年度(4月から翌年3月まで)の実績に基づいて行います。新年度が始まる4月の時点で、前年度の訪問実績を集計し、理学療法士等の訪問回数と看護職員の訪問回数を比較してください。また、3つの加算(緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算)のいずれかを算定しているかも確認が必要です。判定結果は、その年度の報酬算定に反映されます。
Q2年度の途中で看護職員を増員した場合、減算は解除されますか?
残念ながら、年度途中での職員増員では即座に減算は解除されません。前年度の実績に基づく判定のため、当該年度は減算が継続されます。ただし、当年度の訪問実績が改善されれば、翌年度からは減算が解除される可能性があります。そのため、できるだけ早く体制を整え、看護職員による訪問比率を高めることが重要です。
Q3連携型定期巡回の訪問回数はどのように集計すればよいですか?
連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も、前年度の理学療法士等による訪問回数に含まれます。集計の際は、通常の訪問看護の記録と合わせて、連携型サービスの訪問記録も確認してください。職種別(看護職員か理学療法士等か)に分類し、それぞれの訪問回数を正確にカウントすることが必要です。
Q4特別管理加算を算定すれば減算は完全に回避できますか?
はい、特別管理加算、緊急時訪問看護加算、看護体制強化加算のいずれかを算定していれば、理学療法士等の訪問回数が看護職員を上回っていても8単位減算は適用されません。ただし、これらの加算を算定するには、それぞれ特定の要件を満たす必要があります。自事業所の体制や利用者の状況に応じて、最も実現可能な加算を選択し、確実に算定することをお勧めします。
Q5減算によってどの程度収益に影響がありますか?
8単位の減算は、1回の訪問あたり約80円から100円程度の減収となります。例えば、理学療法士等が月に100回訪問している事業所の場合、月額8,000円から10,000円、年間では約10万円から12万円の減収となります。訪問回数が多い事業所ほど影響は大きく、複数の理学療法士等を雇用している事業所では、年間数十万円から数百万円規模の減収になる可能性があります。早期の対策が不可欠です。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
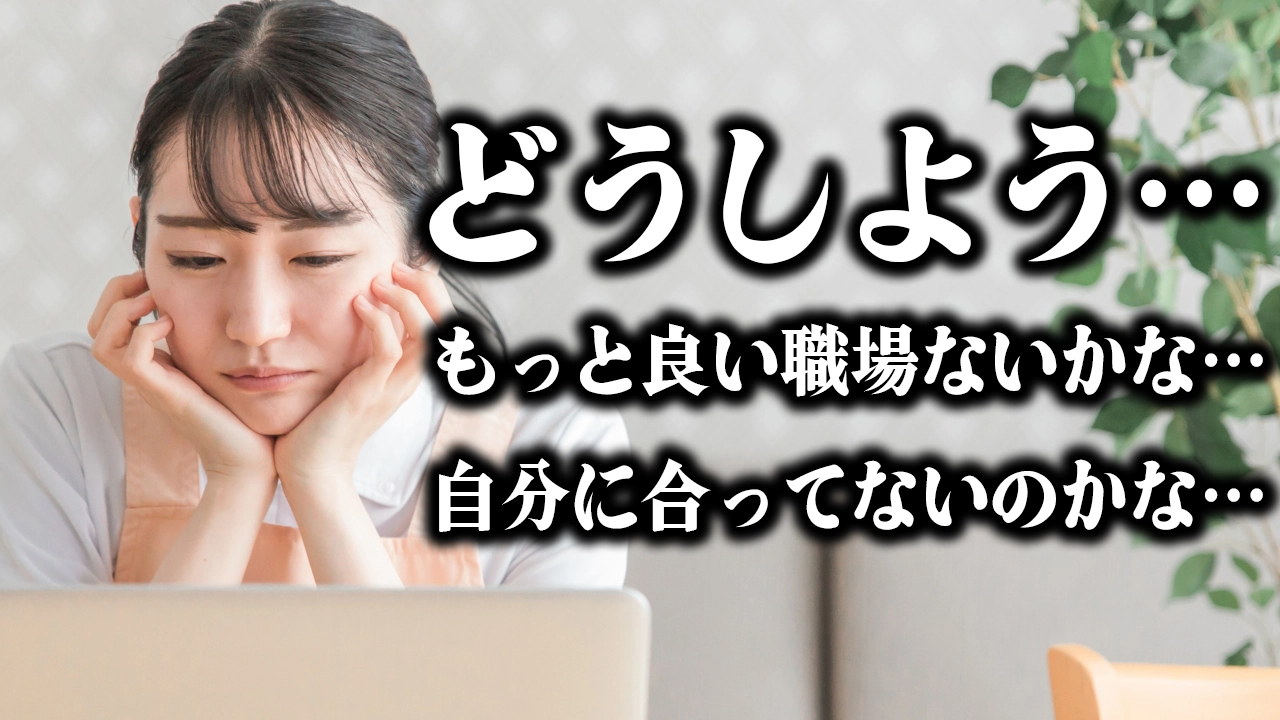
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ今すぐ始める減算対策と持続可能な経営
2024年度の介護報酬改定による減算ルールは、訪問看護ステーションに大きな転換を迫っています。しかし、この改定を単なる脅威として捉えるのではなく、訪問看護本来の機能を見直し、質の高いサービスを提供する事業所へと進化する機会と考えることが重要です。
減算を回避するための5つの実践戦略を着実に実行し、新設・見直しされた加算を戦略的に活用することで、厳しい環境下でも安定した経営を実現できます。特に重要なのは、看護職員による訪問比率を高めること、そして緊急時訪問看護加算などの基本的な加算を確実に算定することです。
今日から、まずは自事業所の前年度実績を正確に把握し、減算対象かどうかを確認してください。そして、長期的な視点で職員配置の見直し、サービス提供体制の強化、利用者セグメンテーションの最適化に取り組むことで、持続可能な経営基盤を築いていきましょう。介護保険制度の改正は今後も続きます。変化に柔軟に対応できる体制こそが、これからの時代に求められる訪問看護ステーションの姿です。




コメント