訪問看護ステーションを運営されている皆さん、介護報酬改定のたびに「うちの事業所はどう影響を受けるんだろう」と不安になっていませんか?報酬体系の変更は、事業所の収益に直結する重要な問題です。実は、改定内容を正しく理解し、適切に対応することで、むしろ収益アップのチャンスにできる可能性があるのです。
この記事では、介護保険改正による訪問看護への影響を徹底的に解説します。看護体制強化加算の新区分、ターミナルケアの評価強化、複数名訪問の拡充など、現場で即実践できる情報をわかりやすくお届けします。最後まで読めば、改定を味方につける具体的な方法が見えてくるはずです。
介護保険改正の4つの柱と訪問看護への影響

介護のイメージ
介護報酬改定は、日本の高齢化社会における医療・介護サービスの質を向上させるために定期的に実施されています。今回の改定では、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止のための質の高い介護サービスの実現、多様な人材確保と生産性の向上、そして介護サービスの適正化と制度の持続可能性の確保という4つの大きな柱が設定されました。
訪問看護にとって特に重要なのは、在宅での医療ニーズが高い要介護者への対応強化です。高齢者の増加に伴い、がん末期や難病を抱えながら自宅で療養を希望される方が増えています。そうした方々に質の高いケアを提供できる体制を整えた事業所を、より高く評価する方向に改定が進んでいるのです。
これは単なる報酬の増減ではありません。事業所の体制づくり、スタッフの育成、他職種との連携など、経営の根幹に関わる変化なのです。だからこそ、改定内容を深く理解し、自事業所の強みを活かせる戦略を立てることが重要になります。
看護体制強化加算の二段階評価で何が変わったのか
看護体制強化加算は、2015年度に創設された加算で、高度な医療を必要とする利用者に対応できる体制を評価するものです。今回の改定で最も注目すべきは、この加算が二段階評価になったことです。
従来の看護体制強化加算は、看護体制強化加算Ⅱとして位置づけられました。そして新たに、ターミナルケアの実施実績が豊富な事業所をさらに高く評価する看護体制強化加算Ⅰが設けられたのです。
具体的な違いを見てみましょう。看護体制強化加算Ⅰを算定するには、直近12ヶ月間にターミナルケア加算を5名以上に算定している必要があります。一方、看護体制強化加算Ⅱは直近12ヶ月間にターミナルケア加算を1名以上算定していることが要件です。
この変更は、在宅でのターミナルケアを積極的に実施している事業所を正当に評価しようという厚生労働省の明確な意思表示です。人生の最終段階を住み慣れた自宅で過ごしたいという利用者のニーズに応えられる事業所ほど、より高い報酬が得られる仕組みになったのです。
経営的な視点で考えると、ターミナルケアの受け入れ体制を整備することが、事業所の収益向上につながる戦略となります。ただし、それは単に収益のためではなく、利用者に最高のケアを提供するための体制づくりが結果として評価されるという、本来あるべき姿を実現するものだと言えるでしょう。
緊急時訪問看護加算の評価アップとその実務への影響
在宅療養を支える上で、緊急時の対応体制は欠かせません。今回の改定では、緊急時訪問看護加算を算定している利用者への2回目以降の緊急訪問についても、評価が強化されました。
特に注目すべきは、早朝・夜間、深夜の加算を算定する場合の要件が緩和されたことです。これにより、夜間や深夜に急変した利用者に対して、より柔軟に対応できる体制が評価されるようになりました。
実務的には、24時間対応体制を整えている事業所にとって追い風となる改定です。オンコール体制の整備、スタッフのローテーション管理、緊急時対応マニュアルの充実など、これまで苦労して構築してきた体制が正当に評価されるようになったのです。
利用者やご家族の立場から見ても、「いつでも相談できる」「必要な時にすぐ来てくれる」という安心感は、在宅療養を継続する上で非常に大きな支えとなります。この改定は、質の高い在宅医療を推進するための重要な一歩と言えるでしょう。
ターミナルケア加算の算定要件変更と人生の最終段階における医療
ターミナルケアとは、余命がわずかとなった方に対して、ご本人が望む最期を実現するために提供する包括的なケアです。痛みなどの苦痛を緩和しながら、できる限り生活の質を保つことを目指します。
今回の改定で重要なのは、人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインの活用が明確に求められるようになったことです。このガイドラインは、患者・医療従事者がともに合意できる基本的な考え方を示したもので、2つの重要な要素から構成されています。
第一の要素は、患者が医療従事者から十分な情報と説明を受けた上で話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本として医療を進めるという原則です。これは、インフォームドコンセントをさらに深化させた概念と言えます。
第二の要素は、意思決定のプロセスを明確化したことです。患者の意思が確認できる場合、できない場合それぞれについて、どのように判断し、誰と相談すべきかが具体的に示されています。
実務においては、利用者やご家族との丁寧なコミュニケーションがより一層重要になります。「どのような最期を迎えたいか」「どこまでの医療処置を希望するか」といった繊細な話題について、信頼関係を築きながら何度も話し合いを重ねる必要があるのです。
算定要件の変更により、このガイドラインに沿った取り組みを記録し、多職種との連携体制を明確にすることが求められています。これは事務的な負担と感じられるかもしれませんが、むしろ利用者の意思を尊重した質の高いケアを提供するための重要なプロセスなのです。
複数名訪問看護に看護補助者の活用が可能に
従来、複数名で訪問看護を実施する場合は、看護師等の複数名による訪問のみが評価されていました。しかし今回の改定で、新たに看護師等と看護補助者による訪問を評価する加算区分Ⅱが創設されました。
看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指導のもとで、療養生活上の世話、居室内の環境整備、看護業務の補助を行う者を指します。重要なのは、特定の資格は必要とされていないという点です。
この変更は、人材不足に悩む訪問看護業界にとって大きな意味を持ちます。すべてのケアを看護師が担う必要はなく、適切な指導体制のもとで業務を分担することで、より多くの利用者にサービスを提供できるようになるのです。
実際の活用例としては、入浴介助や清拭、体位変換の補助、生活環境の整備などが考えられます。看護師は医療的な判断や高度な技術を要するケアに集中し、それ以外の業務を看護補助者と協力して行うことで、効率的かつ質の高いサービス提供が可能になります。
ただし、看護補助者を活用する際には、十分な教育と指導が不可欠です。利用者の安全を第一に考え、適切な役割分担と責任体制を構築することが求められます。
理学療法士等による訪問看護の報酬体系変更
訪問看護ステーションからは、利用者の状態に応じて、看護職員の代わりに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション専門職が訪問することがあります。これらの専門職による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを提供するものです。
今回の改定では、理学療法士等が訪問看護を行った場合の基本報酬に重要な変更がありました。従来はサービス提供時間のみを基準に報酬が区分されていましたが、改定後は要支援の方への提供と要介護の方への提供で報酬が区分されるようになったのです。
この変更の背景には、利用者の要介護度に応じた適切なサービス提供を促進するという狙いがあります。要介護度が高い方ほど、より専門的で複雑なケアが必要となるため、それに見合った報酬体系にすることで、質の高いサービス提供を後押ししているのです。
事業所の経営面では、理学療法士等の配置とその活用方法を見直す良い機会となります。どのような利用者にどのタイミングでリハビリテーション専門職を派遣すべきか、より戦略的に考える必要が出てきました。
同一建物減算の見直しで知っておくべき重要事項
訪問看護の報酬算定において、しばしば複雑で分かりにくいのが同一建物減算です。今回の改定では、この減算の要件が大きく見直されました。
従来は、事業所と同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している方、または同一敷地内ではないが同一の有料老人ホーム等に居住する方20人以上にサービスを提供した場合が減算の対象でした。改定後は、建物の要件が見直され、また利用者の人数による減算率も変更されています。
特に注意が必要なのは、減算対象の利用者と対象外の利用者の公平性を保つための措置です。減算対象者の区分支給限度基準額は、減算前の単位数を使用して計算することになっています。これは一見複雑に見えますが、利用者間の不公平を防ぐための重要な配慮なのです。
実務においては、サービス提供先の建物の状況を正確に把握し、適切に減算を適用することが求められます。誤った算定は返還請求につながる可能性もあるため、請求業務の際には十分な注意が必要です。
精神科訪問看護との併用ルールの明確化
精神疾患を持つ方や心のケアを必要とする方に対して、看護師や精神保健福祉士などが自宅等で相談援助を行うのが精神科訪問看護です。これは医療保険のサービスとして提供されます。
従来から、同一日に介護保険の訪問看護と医療保険の精神科訪問看護を併用して算定することはできないとされていました。しかし、この取り決めは厚生労働省の事務連絡によるもので、明文化されていなかったのです。
今回の改定では、介護報酬告示においても併用算定できない旨が明確化されました。これにより、現場での解釈の混乱を防ぎ、適切な算定を促進することが期待されています。
ただし、月の途中で利用者の状態が変化した場合など、医療保険による精神科訪問看護から介護保険の訪問看護へ変更することは可能です。重要なのは、状況に関わらず数日単位で医療保険と介護保険を交互に利用することはできないという点です。
精神疾患を抱える利用者のケアでは、医療と介護の連携が特に重要になります。どちらの保険で対応するのが最適か、ケアマネジャーや主治医と密に連絡を取りながら判断することが求められます。
介護保険改正と訪問看護に関する疑問解決
看護体制強化加算ⅠとⅡの違いは何ですか?
最も大きな違いは、ターミナルケア加算の算定実績です。看護体制強化加算Ⅰは直近12ヶ月間に5名以上、加算Ⅱは1名以上のターミナルケア加算算定が必要です。加算Ⅰの方がより高い評価を受けられますが、その分、在宅でのターミナルケアを積極的に実施している実績が求められます。小規模な事業所でも、質の高いターミナルケアを継続的に提供していれば、段階的に加算Ⅰを目指すことができます。
看護補助者には具体的にどのような業務を任せられますか?
看護補助者は、看護師の指導のもとで療養生活上の世話、居室内の環境整備、看護業務の補助を行います。具体的には、入浴介助の補助、清拭、体位変換の補助、ベッドメイキング、生活環境の整理整頓などです。医療的判断を伴う業務や、高度な技術を要するケアは看護師が担当し、それ以外の業務を適切に分担することで、効率的なサービス提供が可能になります。
理学療法士等による訪問で報酬が変わったのはなぜですか?
要介護度に応じた適切なサービス提供を促進するためです。要介護度が高い方ほど、より専門的で複雑なリハビリテーションが必要となります。これまでは提供時間のみで報酬が決まっていましたが、改定後は要支援者と要介護者で報酬が区分されることで、利用者の状態に応じたきめ細やかなケアを評価する仕組みになりました。
同一建物減算の対象かどうかはどう判断すればよいですか?
まず、サービス提供先の建物が有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに該当するか確認します。次に、その建物で訪問看護を受けている利用者の人数を把握します。事業所と建物の位置関係、利用者数によって減算率が決まるため、正確な情報収集が不可欠です。不明な点がある場合は、各自治体の担当窓口に確認することをお勧めします。
人生の最終段階における医療の決定プロセスガイドラインは具体的にどう活用すればよいですか?
まず、利用者やご家族との信頼関係を構築することから始めます。そして、十分な情報提供と説明を行った上で、利用者本人の意思を確認する話し合いの場を設けます。その内容を記録に残し、医師や他の医療・介護スタッフと共有します。利用者の意思が変わることもあるため、継続的に話し合いを重ねることが重要です。このプロセス自体が、質の高いターミナルケアの基盤となるのです。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
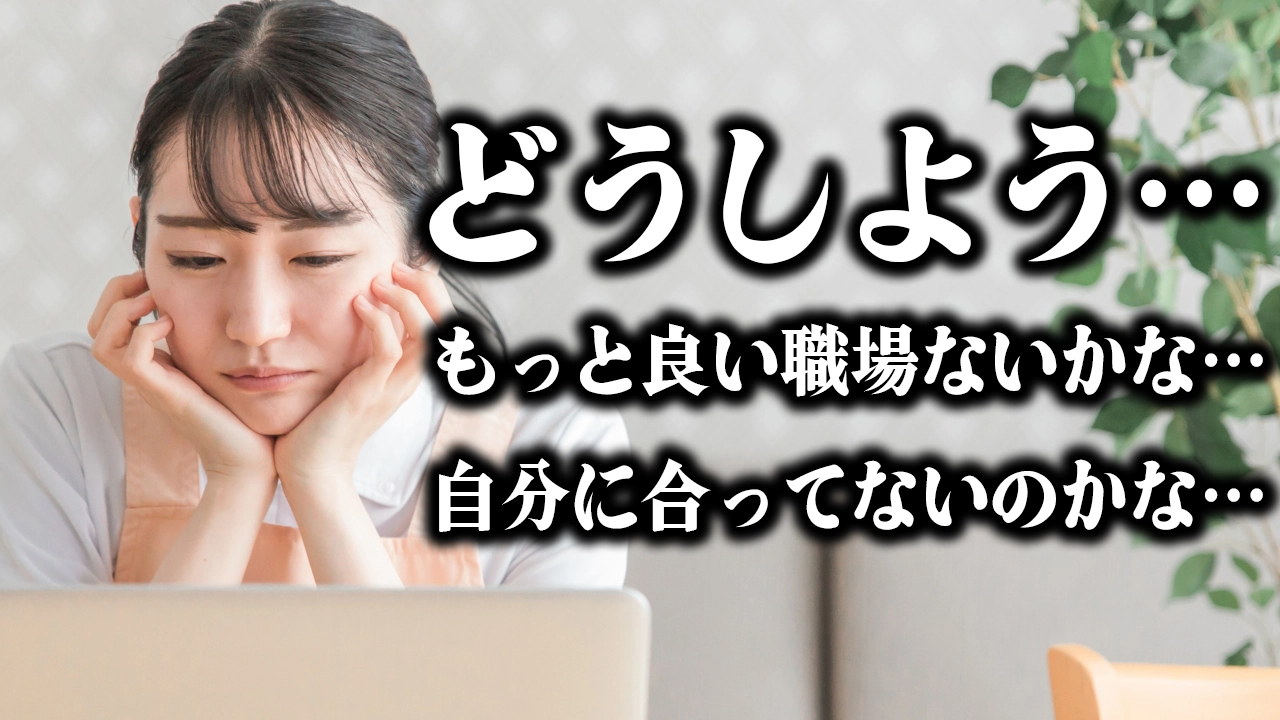
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ介護保険改正を事業所成長の機会に変える
介護保険改正は、訪問看護事業所にとって大きな転換点です。看護体制強化加算の二段階評価、緊急時訪問看護の評価強化、看護補助者の活用、理学療法士等の報酬体系変更など、今回の改定は在宅医療の質向上を明確に目指しています。
重要なのは、これらの変更を単なる報酬の増減として捉えるのではなく、利用者により良いケアを提供するための体制づくりの機会として活用することです。ターミナルケアの受け入れ体制整備、24時間対応の充実、多職種協働の推進など、改定が評価する方向性は、まさに訪問看護の本質的な価値を高める取り組みそのものなのです。
今すぐできることから始めましょう。スタッフとの情報共有、体制の見直し、算定要件の確認など、一つひとつ着実に進めることで、改定を事業所の成長につなげることができます。利用者の笑顔と事業所の発展、その両方を実現するために、この改定を最大限に活用してください。




コメント