介護の仕事を探していて「準夜勤」という言葉を見かけたものの、具体的にどんな時間帯で働くのか、どんな業務をするのか、よく分からないという方は多いのではないでしょうか。実は、準夜勤は通常の夜勤とは異なる特徴を持ち、ライフスタイルに合わせた働き方ができる魅力的な勤務形態なんです。今回は、介護職の準夜勤について、時間帯から給与、業務内容、そして向き不向きまで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。これから介護の仕事を始めたい方、準夜勤に興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
介護の準夜勤とは?基本を理解しよう

介護のイメージ
まず、準夜勤という言葉を初めて聞いた方のために、基本的な概念から説明していきますね。
準夜勤の定義と時間帯
準夜勤とは、夜間帯の一部をカバーする勤務形態のことを指します。一般的な準夜勤の時間帯は22時から翌朝7時までで、休憩時間を含めて約9時間の勤務となります。この時間帯は、施設のご利用者様が就寝される時間から起床される時間までをカバーしており、安全で快適な睡眠環境を提供するための重要な役割を担っています。
準夜勤という名称は施設によって異なることもあり、「夜勤」「遅番」などと呼ばれることもありますが、基本的には深夜から早朝にかけての時間帯を担当する勤務であることは共通しています。通常は週2日程度の勤務から始めることができ、家庭との両立やWワークを希望される方にも人気の働き方です。
夜勤との違いを知っておこう
ここで多くの方が疑問に思うのが、「準夜勤」と「夜勤」の違いです。実は、これらは似ているようで異なる概念なんです。一般的な夜勤は16時間や24時間などの長時間勤務を指すことが多く、日中から翌朝まで通しで働くケースがあります。一方、準夜勤は夜間の時間帯に特化した8~9時間程度の勤務で、比較的短時間で集中して働くことができます。
また、業務内容も異なります。通常の夜勤では夕食介助から始まり、就寝介助、夜間の見守り、起床介助、朝食介助まで幅広い業務を担当しますが、準夜勤では主に就寝後の見守りや夜間対応に特化しているのが特徴です。
準夜勤の具体的な勤務時間と休憩
それでは、より具体的に準夜勤の時間について見ていきましょう。
標準的な勤務時間の内訳
準夜勤の標準的な勤務時間は22時から翌朝7時までです。この9時間の中には、労働基準法に基づいた休憩時間60分が含まれています。つまり、実働時間は8時間ということになります。22時に出勤し、施設の日勤スタッフから申し送りを受けて業務を開始します。夜間を通してご利用者様の安全を見守り、翌朝7時に日勤スタッフへ申し送りをして勤務終了となります。
この時間帯の設定には理由があります。多くのご利用者様は22時頃までには就寝されるため、その後の夜間帯を安全に過ごしていただくための体制が必要になります。また、朝7時までには起床介助を始める必要があるため、この時間帯での勤務が最も効率的なんです。
休憩時間の取り方と工夫
60分の休憩時間は、通常は夜間の業務が落ち着いている時間帯、例えば深夜2時から3時頃に取ることが多いです。ただし、介護の現場では予期せぬことが起こる可能性があるため、休憩中でも緊急時には対応できる体制を取っています。休憩室で仮眠を取ったり、軽食を取ったりしながら、次の業務に備えて体力を回復させます。
施設によっては、複数のスタッフが準夜勤に入る場合、交代で休憩を取ることで、常にご利用者様の安全を確保しています。この休憩時間の使い方が、長時間の夜間勤務を乗り切るための重要なポイントになります。
準夜勤の業務内容を詳しく解説
準夜勤では具体的にどんな仕事をするのか、詳しく見ていきましょう。
主な業務内容とその重要性
準夜勤の業務は、ご利用者様が安心して夜を過ごせるようにサポートすることが中心です。具体的な業務内容としては、定期的な巡視、排泄介助、体位変換、コール対応、寝付けない方への傾聴、緊急時の対応、そして記録業務などがあります。
巡視では、各居室を定期的に回り、ご利用者様の状態を確認します。呼吸の状態、体温、表情などを観察し、異変がないかをチェックします。排泄介助は、夜間でもトイレに行きたい方や、おむつ交換が必要な方へのサポートを行います。体位変換は、褥瘡(床ずれ)予防のために、2時間おきに体の向きを変える重要な業務です。
コール対応では、ナースコールが鳴ったら迅速に駆けつけ、ご利用者様のニーズに応えます。また、なかなか眠れない方には、優しく話を聞いたり、温かい飲み物をお持ちしたりして、安心して眠れるようにサポートします。これらすべての業務について、詳細な記録を残すことも大切な仕事の一つです。
時間帯別の業務の流れ
22時から23時頃は、日勤スタッフからの申し送りを受け、夜間の体制に入る準備をします。まだ起きているご利用者様もいらっしゃるため、就寝のサポートや最終的なトイレ介助を行います。23時から深夜2時頃までは、定期的な巡視と必要に応じた介助を行う時間です。この時間帯が最も集中力が必要で、静かな環境の中で細やかな観察が求められます。
深夜2時から4時頃は、休憩を取りながら引き続き巡視を続けます。4時から7時は、徐々に起床時間に向けた準備を始めます。早朝にトイレに行かれる方のサポートや、起床介助の準備などを行い、7時には日勤スタッフへの申し送りを行って勤務を終えます。
準夜勤の給与と待遇について
気になる給与面についても、しっかりと確認しておきましょう。準夜勤の給与体系は、日給制を採用している施設が多く、一回の勤務につき12,000円から15,000円程度が相場となっています。この金額は、保有資格によって変動することが一般的です。
例えば、認知症基礎研修を修了している方は日給12,000円、介護福祉士の資格をお持ちの方は日給15,000円というように、資格や経験に応じて給与が設定されます。さらに、処遇改善手当が別途支給される施設も多く、実際の手取り額はこれらを合わせた金額になります。
週2日勤務の場合、月8回程度の勤務となり、月収としては96,000円から120,000円程度になります。これに加えて、年末年始手当(12月30日から1月3日は1日あたり3,000円)や交通費支給(上限30,000円/月)などの福利厚生も充実しています。Wワークや副業として準夜勤を選択される方にとって、短時間で効率的に収入を得られる魅力的な働き方と言えるでしょう。
準夜勤のメリットとデメリット
準夜勤での働き方には、良い面も大変な面もあります。両面を理解した上で、自分に合っているかを判断することが大切です。
メリットとしては、まず日中の時間を自由に使えることが挙げられます。お子さんの学校行事に参加したり、日中に銀行や役所での用事を済ませたりできます。また、比較的短時間の勤務で高収入を得られることも魅力です。夜間は職員数が少ないため、落ち着いた環境で丁寧なケアができるという点も、介護の仕事にやりがいを感じる方には大きなメリットでしょう。
さらに、準夜勤は週2日程度から始められるため、家庭との両立やWワークがしやすいという柔軟性があります。夜型の生活リズムが合っている方にとっては、自分の体質に合った働き方ができます。
一方、デメリットとしては、生活リズムの調整が必要になることです。夜間に働くため、睡眠時間を日中に取る必要があり、最初は体調管理が難しいと感じる方もいらっしゃいます。また、家族や友人との時間が合わせにくくなることもあります。
夜間は緊急時に即座に対応しなければならないため、責任の重さとプレッシャーを感じることもあるでしょう。少人数体制での勤務となるため、チームワークと個人の判断力の両方が求められます。体力的にも、夜間に起きていることへの慣れが必要です。
準夜勤に向いている人の特徴
準夜勤は誰にでも合う働き方というわけではありません。自分に向いているかどうかを判断するために、適性について考えてみましょう。
準夜勤に向いているのは、夜型の生活リズムが苦にならない方です。もともと夜遅くまで起きていることが多い方や、朝が苦手な方には適しています。また、冷静な判断力と責任感がある方も向いています。夜間は管理者がいないことも多く、自分で判断して行動する場面が多いため、落ち着いて対応できる力が必要です。
観察力が鋭く、細かな変化に気づける方も準夜勤に適しています。夜間の静かな環境だからこそ、ご利用者様のわずかな変化や異常に気づくことができる観察眼が大切です。また、傾聴力がある方も重要です。眠れない方の話を丁寧に聞き、安心感を与えられるコミュニケーション能力が求められます。
さらに、日中に自分の時間を持ちたい方、副業やWワークを考えている方、家族の介護や育児で日中は忙しい方なども、準夜勤という働き方を選択肢として考える価値があります。柔軟な働き方を実現したい方にとって、準夜勤は理想的な選択肢となる可能性があります。
介護準夜勤時間に関する疑問解決
ここでは、準夜勤について多くの方が疑問に思うことをQ&A形式で解説していきます。
準夜勤は未経験でも始められますか?
はい、未経験でも準夜勤を始めることは可能です。多くの施設では、準夜勤に入る前に日勤帯で数日間研修を行い、施設の雰囲気や業務内容、ご利用者様の特徴などを学んでから夜間勤務に入る体制を整えています。認知症基礎研修や実務者研修などの資格を取得していれば、さらにスムーズに業務を始められます。最初は先輩スタッフと一緒に勤務し、徐々に独り立ちしていく流れが一般的ですので、安心してスタートできますよ。
準夜勤の勤務日数は調整できますか?
はい、多くの施設では週2日程度から勤務可能で、曜日や勤務日数について相談に応じてくれます。家庭の事情や他の仕事との兼ね合いを考慮して、柔軟にシフトを組んでもらえる施設が増えています。ただし、施設側も安定した人員確保が必要なため、あまりにも不規則な勤務希望には対応できない場合もあります。面接時に具体的な希望を伝え、双方にとって無理のない働き方を相談することが大切です。
準夜勤中に仮眠は取れますか?
休憩時間(60分)中に仮眠を取ることは可能です。多くの施設には休憩室や仮眠室が用意されており、そこで体を休めることができます。ただし、完全に熟睡するのではなく、緊急時にはすぐに対応できる状態を保つことが求められます。短時間でも質の良い休息を取ることで、勤務後半の集中力を維持できます。仮眠の取り方や休憩室の使い方については、入職時にしっかりと説明を受けることができますので、心配はいりません。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
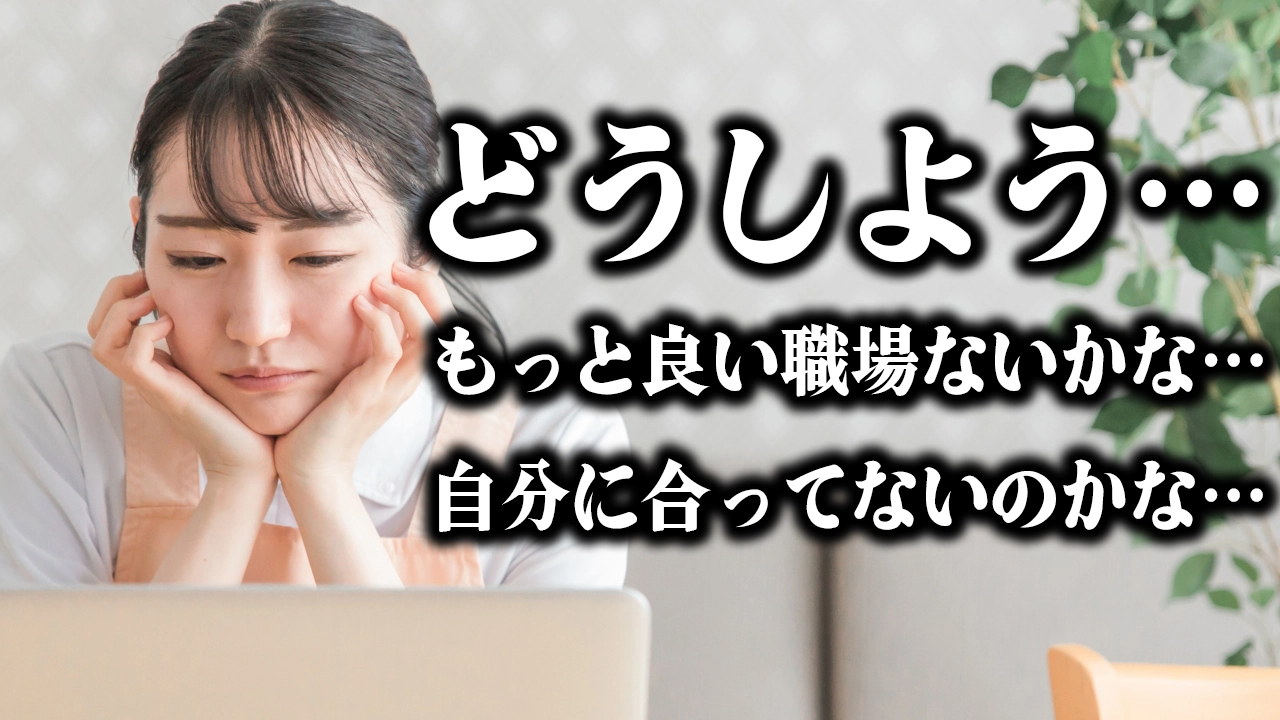
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ
介護の準夜勤は、22時から翌朝7時までの時間帯で、ご利用者様の夜間の安全と快適さを守る重要な仕事です。週2日程度から始められる柔軟な働き方で、日給12,000円から15,000円という収入を得ることができます。業務内容は巡視や排泄介助、体位変換など多岐にわたりますが、夜間という落ち着いた環境で丁寧なケアができることが魅力です。
日中の時間を有効活用したい方、夜型の生活リズムが合っている方、Wワークや副業を考えている方にとって、準夜勤は理想的な働き方となる可能性があります。一方で、生活リズムの調整や責任の重さなど、考慮すべき点もあります。自分のライフスタイルや体質、キャリアプランをよく考えた上で、準夜勤という働き方を選択肢の一つとして検討してみてください。
興味を持たれた方は、まず施設見学や面接に参加して、実際の雰囲気や働き方について詳しく聞いてみることをお勧めします。あなたに合った働き方が、きっと見つかるはずです。

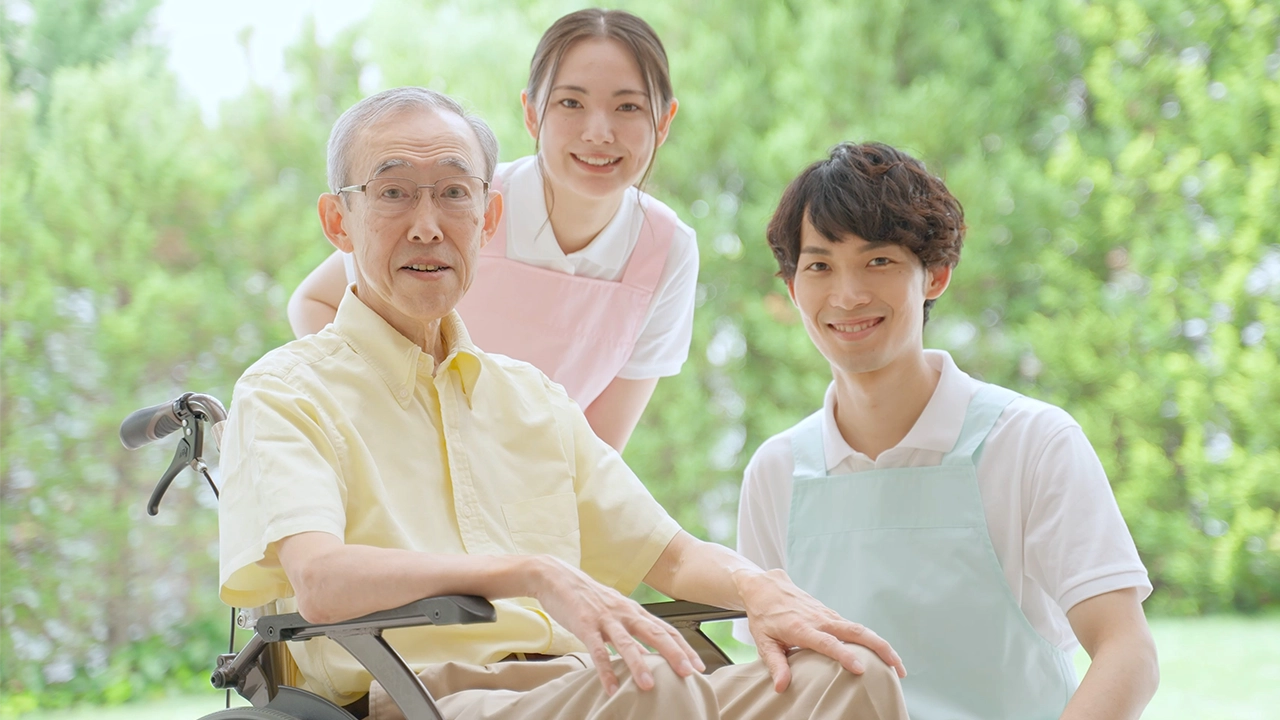


コメント