「親の介護が始まったけど、在宅介護ってどれくらい費用がかかるんだろう?」
漠然とした不安を抱えてこの記事にたどり着いたあなたは、まさにこれから介護費用という大きな壁に直面しようとしています。多くの人が「在宅介護は施設入所より安上がり」と考えていますが、それは大きな勘違いかもしれません。公的な統計データだけを見て安心していると、思わぬ出費に頭を抱えることになる可能性があります。
このブログでは、在宅介護にかかる費用の全体像から、多くの人が見落としがちな3つの「隠れた出費」、そして介護費用を賢く捻出するための具体的な対策まで、他の記事では語られない「生の声」と圧倒的に価値のある情報を余すことなくお伝えします。最後まで読めば、あなたの介護費用に対する不安はきっと解消されるでしょう。
在宅介護にかかる費用、その全体像を徹底解説!

介護のイメージ
在宅介護にかかる費用は、大きく分けると3つの要素で構成されています。まずはこの全体像をしっかりと把握しましょう。
介護保険サービス費(自己負担分)
これは、訪問介護やデイサービス、ショートステイなど、介護保険が適用されるサービスを利用した際に発生する費用です。要介護度に応じて利用できるサービスの量が決まっており、自己負担割合は所得に応じて1割から3割となっています。
たとえば、要介護3の方がデイサービスを週に2回利用し、さらに訪問介護を週に3回利用するといった場合、月々の利用限度額の範囲内でこの費用を支払うことになります。利用するサービスの組み合わせや回数によって費用は変動しますが、これが在宅介護費用のベースとなります。
介護用品費
在宅介護では、様々な介護用品が必要になります。介護ベッドや車椅子、歩行器、手すりなどのレンタル・購入費用に加え、日常的に使うおむつやパッド、口腔ケア用品、栄養補助食品など、細々とした出費が積み重なります。
介護保険を利用すれば、一部の福祉用具は1割から3割の自己負担でレンタルできますが、すべてが対象になるわけではありません。また、おむつ代などは医療費控除の対象になる場合もありますが、基本的には自己負担となることが多いでしょう。
その他の費用(見落としがちな隠れた出費)
ここが最も重要であり、多くの人が見落としがちな部分です。介護保険適用外の費用や、生活費の中で介護に関連して増える出費がこれにあたります。
たとえば、在宅介護に伴う住宅改修費(手すりの設置、段差解消など)や、通院や買い物などで発生する交通費、遠方に住む家族の帰省費用、さらには介護者の代わりに行う家事代行サービスや配食サービス費用なども含まれます。在宅介護では、これらの「見えない出費」が意外なほど家計を圧迫することがあります。
在宅介護の費用を賢く乗り切る!知らないと損する3つのポイント
在宅介護の費用を考える上で、絶対に押さえておくべき3つのポイントを深掘りしていきましょう。これを知っているかどうかで、介護生活の経済的な負担は大きく変わります。
ポイント1公的統計の「平均値」だけを鵜呑みにしない!
元の文章にもあったように、生命保険文化センターの調査では在宅介護の月額費用平均は4.8万円とされています。しかし、この数字はあくまで「平均」に過ぎません。介護の状況は家族ごとに千差万別で、この金額を大幅に超えるケースも少なくありません。
たとえば、要介護度が重くなり医療的なケアが必要になったり、介護者自身の仕事との両立が難しくなり外部サービスに頼らざるを得なくなったりすれば、費用はあっという間に跳ね上がります。この平均値に加えて、万が一の出費や介護者の経済的な負担も考慮に入れた計画を立てることが何よりも大切です。
ポイント2在宅介護は「施設より安い」とは限らない!
多くの方が「在宅介護は施設入所より安い」と考えがちですが、これは大きな誤解です。確かに、介護サービス費だけを見れば在宅の方が安価に見えるかもしれません。しかし、在宅介護では介護者の時間や労力という「見えないコスト」が発生します。
介護のために仕事をセーブしたり辞めたりすれば、収入は激減します。また、介護者が一人で全てを担おうとすれば、心身の疲労から体調を崩し、結果的に医療費がかさんでしまうこともあります。施設入所にかかる費用には、24時間体制の介護、居住費、食費、そしてプロの管理による安心感というコストが含まれています。単純な金額比較ではなく、トータルでかかる費用と負担を総合的に評価することが重要です。
ポイント3介護は「家族全員の問題」と捉える!
「親の介護費用は親の貯金でまかなうのが当たり前」と考えていませんか?もちろん、それが基本ではありますが、高齢になった親御さんの資産状況は不透明なことが多く、いざという時に「全くお金がなかった」というケースも珍しくありません。
介護費用を一人で抱え込まず、兄弟姉妹や親戚とオープンに話し合うことが不可欠です。親御さんの財産状況を把握するだけでなく、誰がどの程度の負担を担うのか、役割分担を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。介護は突然やってくるもの。そうなる前に、家族全員で費用について話し合い、共通認識を持つことが重要です。
プロが教える!介護費用を劇的に軽減する4つの制度
公的な支援制度や助成金を活用すれば、介護費用は大きく軽減できます。しかし、これらの制度は「申請主義」のため、知っていて自ら行動しなければ利用できません。ここでは、特に重要な4つの制度をわかりやすく解説します。
高額介護サービス費
これは、1ヶ月の介護保険サービス利用料が所得に応じた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。所得が低いほど上限額は低く設定されています。この制度を活用すれば、月々の介護サービス利用料の負担を劇的に減らすことができます。たとえば、要介護度の高い方が集中的なサービスを利用しても、自己負担額が一定額を超える心配はほとんどありません。
高額医療合算介護サービス費
医療費と介護費の両方が高額になった場合に利用できる制度です。1年間にかかった医療費と介護費の自己負担額を合計し、所得に応じた上限額を超えた分が払い戻されます。介護と医療の両方に費用がかかる方にとって、非常に心強い制度です。毎年8月1日から翌年7月31日の期間で計算され、申請が必要です。
医療費控除
これは確定申告で利用する制度です。介護サービス費用の中には、医療費控除の対象となるものがあります。例えば、訪問看護サービスや、医師の証明書があればおむつ代なども対象になります。領収書には「医療費控除対象額」と記載されていることが多いので、確認してみましょう。
自治体独自のサービス
見落とされがちですが、市区町村によっては独自の支援サービスが用意されています。紙おむつ代の助成、配食サービス、訪問理美容サービスなど、その内容は地域によって様々です。インターネットで「(お住まいの地域名) 介護 助成」と検索したり、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談したりすることで、思わぬ助成制度が見つかるかもしれません。
介護に関する疑問解決!よくある質問にプロが回答
### Q. 親が介護について話してくれません。どうやってお金の話を切り出せばいいですか?
A. 非常に多くの方が悩む問題です。いきなり「財産はいくらあるの?」と聞くのは避けた方が無難です。まずは「自分の老後の準備について相談したいんだけど…」と切り出してみるのはいかがでしょうか。自分の話をすることで、親御さんも安心して話してくれるきっかけになります。
### Q. 介護休業給付金は、雇用保険に加入していれば誰でももらえますか?
A. 支給要件を満たす必要があります。具体的には、介護のために2週間以上休業すること、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることなどが挙げられます。詳細は勤務先の担当者やハローワークに確認してみましょう。
### Q. 介護の相談は誰にすればいいですか?
A. まずは、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。彼らは地域の介護情報や利用できる制度に精通している、いわば介護のプロフェッショナルです。不安な気持ちを一人で抱え込まず、プロの力を借りることが早期解決への近道となります。
今すぐ介護の悩みを解決したい!どうしたらいい?

「親族の介護、もう待てない状況になっていませんか?」
介護は突然やってきます。「まだ大丈夫」と思っていても、転倒や急な体調変化で一気に現実となることも。
そんな時、慌てて施設を決めて後悔しないために。
もちろん、今介護で悩んでいる人であってもどの施設であればすぐに入れるのかを事前に情報収集する必要があります。
そんなとき「みんなの介護」なら、業界最大手の安心感と51,000件という圧倒的な選択肢で、あなたがどんな状況でもベストな施設が見つかります。
⭐ 掲載施設数No.1の実績
⭐ 経験豊富な相談員が24時間サポート
⭐ 見学予約から入居まで完全無料でフォロー
「あの時、もっと調べておけば良かった」
そんな後悔をしないために、今すぐ行動を。
複数施設の資料を取り寄せて、ご家族で安心できる選択をしませんか?
▼無料資料請求はこちら▼
資料請求はこちら
![]()
まとめ介護費用は「備え」が9割。今すぐ行動して不安を解消しよう
在宅介護サービスにかかる費用は、単に介護保険の自己負担分だけではありません。介護用品費や、見落としがちな「隠れた出費」を含めた全体像を把握し、家族でしっかりと話し合うことが何よりも大切です。
「うちは大丈夫」と安易に考えず、公的な統計の数字に惑わされず、このブログで紹介した4つの制度や、家族での話し合いの場を設けるなど、今すぐできる行動から始めてみてください。介護はいつか必ずやってくる未来です。その時のために賢く備えることが、あなたとあなたの家族の安心な生活を守ることにつながります。



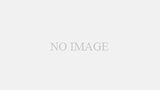
コメント