令和7年1月22日、厚生労働省から重要な通知が発表されました。介護保険法施行令の一部改正が公布され、4月1日から施行されることになったのです。「年金が増えたのに、なぜ介護保険料の基準が変わるの?」多くの方がこの疑問を抱いているのではないでしょうか。
実は、この改正にはあなたの家計を守る重要な配慮が隠されています。さらに、8月からは一部の介護施設で新たな負担が始まることも決定しました。この記事では、介護保険改正令和7年の全貌を、現場の専門家の視点から徹底解説します。読み終える頃には、あなたとご家族が今すぐ確認すべきことが明確になるはずです。
令和7年介護保険改正の全体像を3分で理解する

介護のイメージ
今回の改正は、大きく分けて2つの重要な変更点があります。一つは令和7年4月から施行される介護保険料の基準額調整、もう一つは8月から始まる一部施設の室料負担導入です。
改正のタイミングと影響範囲
令和7年4月1日施行の変更では、全国の65歳以上の第1号被保険者が対象となります。特に影響を受けるのは、介護保険料の第1段階、第2段階、第4段階、第5段階に該当する方々です。これは数百万人規模の高齢者に関わる重要な改正なのです。
一方、令和7年8月1日施行の変更は、特定の介護施設に入所している約8,000人の方が対象となります。対象施設はII型介護医療院、療養型老健、その他型老健の多床室です。
知られざる保険料基準額変更の本当の理由
老齢基礎年金の増額が招いた問題
令和6年の老齢基礎年金(満額)の支給額は809,000円となりました。これは一見喜ばしいニュースですが、実は大きな問題を引き起こす可能性がありました。
なぜなら、介護保険料の段階判定には「年金収入80万円以下」という基準が設定されていたからです。この基準は平成18年度に設定されたもので、当時の老齢基礎年金満額支給額792,100円を基に決められていました。
年金が増額されると、これまで第1段階だった方が第2段階に、第4段階だった方が第5段階に上がってしまい、年金が増えたのに手取りが減るという逆転現象が起きる恐れがあったのです。
公平性を保つための基準額調整
この問題を解決するため、国は迅速に対応しました。年金収入の基準額を80万円から80.9万円(809,000円)に引き上げることで、年金の増額による意図しない保険料負担増を防いだのです。
この改正により、該当する高齢者の方々は年金の増額分を実質的に受け取ることができます。制度の公平性を維持しながら、高齢者の生活を守るという国の姿勢が表れた改正と言えるでしょう。
8月から始まる多床室室料負担の衝撃
月額8,000円の新たな負担とは
令和7年8月1日から、一部の介護施設で多床室の室料負担が新たに導入されます。対象となるのは以下の施設です。
対象施設は、II型介護医療院の多床室利用者約4,000人、療養型老健の多床室利用者約2,000人、その他型老健の多床室利用者約2,000人の合計約8,000人です。これらの方々は、1日あたり260円、月額にして約8,000円の室料を新たに負担することになります。
ただし、すべての入所者が対象となるわけではありません。多床室でも1人あたりの居室面積が8平方メートル以上の場合に限られます。
なぜ今、室料負担が導入されるのか
この改正の背景には、在宅介護との公平性という大きなテーマがあります。特別養護老人ホームでは既に2015年度から一定以上の所得がある利用者に室料負担が課されていましたが、老健や介護医療院は対象外でした。
しかし、これらの施設が本来の在宅復帰や医療的ケアの提供という役割を超え、実質的な生活の場となっているケースが増えています。在宅で介護を受ける方との負担の公平性を図り、また増大する介護保険財政を持続可能にするため、今回の改正が決定されました。
あなたは対象者?今すぐ確認すべきこと
保険料基準額変更の影響チェックリスト
令和7年4月からの基準額変更により、影響を受ける可能性があるのは以下の条件に当てはまる方です。65歳以上で介護保険料の第1段階、第2段階、第4段階、第5段階に該当している方、公的年金収入が年間80万円前後の方、市町村民税非課税または非課税世帯の方が該当します。
ご自身やご家族が該当するか不明な場合は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に確認することをおすすめします。6月に送付される介護保険料納入通知書で、新しい保険料額を確認できます。
室料負担の対象施設と減免措置
8月からの室料負担について、最も重要なのは低所得者への配慮措置です。補足給付を受けている利用者、つまり利用者負担第1段階から第3段階に該当する方については、負担が増えないような措置が講じられます。
具体的には、生活保護受給者の方、市町村民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方、市町村民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下の方は、補足給付により実質的な負担増がありません。
介護保険制度の今後の展望と備え方
2027年度に向けた大きな制度改正
実は、今回の改正は序章に過ぎません。2024年12月から、2027年度の介護保険法改正に向けた審議が社会保障審議会介護保険部会で始まっています。これは例年より4ヶ月も早いスタートで、それだけ改正の規模が大きいことを示しています。
検討されている主な項目には、利用者負担2割の範囲拡大の検討(2027年度の第10期計画期間開始前までに結論)、ケアマネジメントの給付のあり方の見直し、軽度者への生活援助サービスに関する給付の検討、介護職員の処遇改善のさらなる推進などがあります。
今からできる具体的な準備
今後の制度変更に備えるため、今からできることがあります。まず、ご自身やご家族の介護保険料の段階を正確に把握しましょう。毎年6月に送付される通知書を必ず確認してください。
介護施設に入所されている方や入所を検討している方は、施設のタイプを確認することが重要です。強化型や加算型の老健は今回の室料負担の対象外ですが、その他型や療養型は対象となります。
将来の負担増に備えて、介護保険外サービスの活用も検討の価値があります。緊急時の対応や柔軟なサービス利用が可能な保険外サービスは、2030年には318万人のビジネスケアラーを支える重要な選択肢となると予測されています。
介護保険改正令和7年に関する疑問解決
介護保険料の基準額変更で私の保険料は上がるの?
基準額の変更により、多くの方の保険料は変わらないか、むしろ実質的に負担が軽減されます。これは年金増額による意図しない保険料段階の上昇を防ぐための措置だからです。ただし、市町村ごとに設定される基準額自体が第9期計画(令和6年度から令和8年度)で見直されている場合は、別の理由で保険料が変更されている可能性があります。
多床室の室料負担は全員が対象なの?
いいえ、対象は限定的です。まず、施設のタイプが重要で、II型介護医療院、療養型老健、その他型老健のみが対象です。強化型や加算型の老健は対象外です。さらに、利用者負担第1段階から第3段階の方は補足給付により負担増はありません。実際に新たな負担が発生するのは、全国の老健・介護医療院入所者のうち約8,000人と推計されています。
今後さらに介護の自己負担は増えるの?
政府は2027年度の第10期介護保険事業計画期間の開始前までに、利用者負担2割の範囲拡大について結論を出す方針です。現在、一定以上の所得がある方は2割または3割負担ですが、その範囲が拡大される可能性があります。また、ケアマネジメントの利用料徴収や、要介護1・2の生活援助サービスの総合事業への移管なども議論されています。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
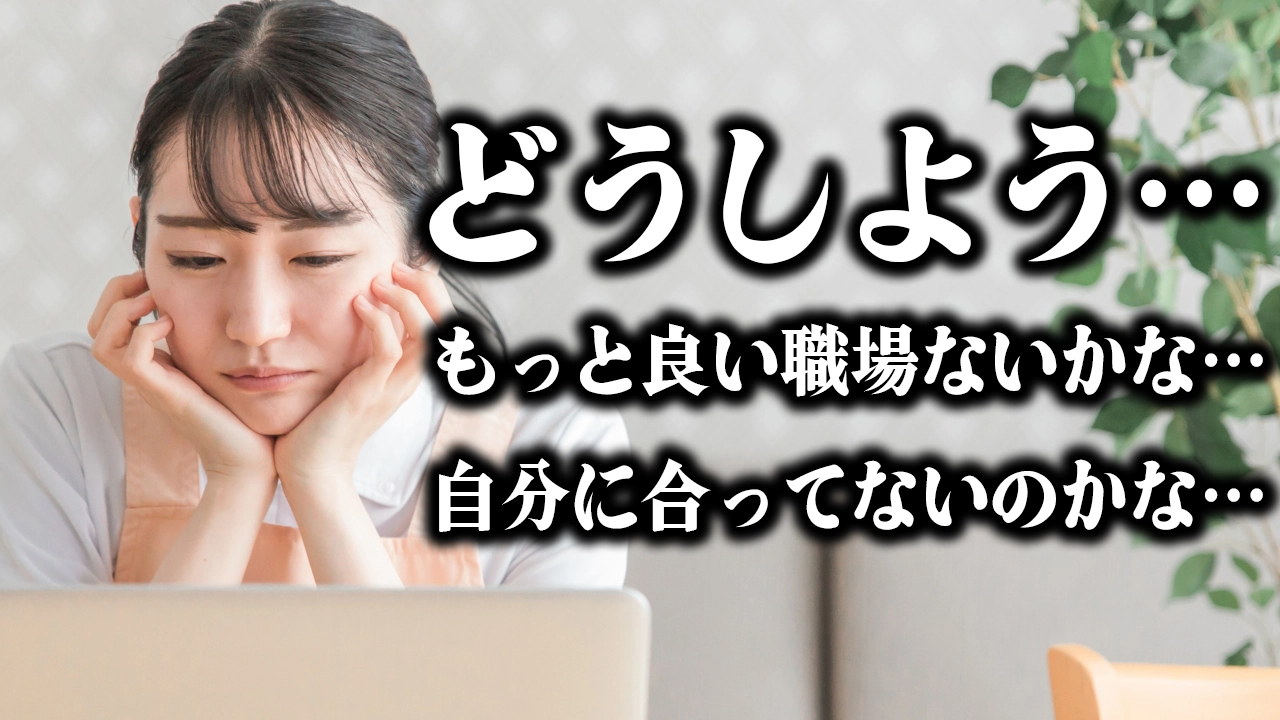
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめ:令和7年改正を機に介護の備えを見直そう
令和7年の介護保険改正は、制度の公平性と持続可能性を目指した重要な一歩です。4月からの保険料基準額変更は、年金増額による意図しない負担増を防ぐための配慮であり、多くの高齢者にとって実質的な負担軽減となります。
8月からの多床室室料負担導入は、約8,000人の方に影響しますが、低所得者への配慮措置も整備されています。在宅介護との公平性を図り、増大する介護給付費に対応するための措置と理解できます。
最も重要なのは、2027年度に向けてさらに大きな制度改正が予定されていることです。利用者負担の範囲拡大やケアマネジメントの見直しなど、家計に直接影響する変更が議論されています。
今こそ、ご自身やご家族の介護保険料の段階を確認し、将来の介護に備えて情報収集を始める絶好のタイミングです。市町村の窓口やケアマネジャーに相談し、あなたの状況に合った最適な準備を進めていきましょう。介護保険制度は複雑ですが、正しく理解し活用することで、安心した老後生活を送ることができます。




コメント