介護の現場で働くあなた、有給休暇をしっかり取得できていますか?「人手不足だから休めない」「管理職になったら有給が取りにくくなった」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、令和5年度に実施された大規模な介護労働実態調査で、介護職の有給取得率は平均53.7%という衝撃的な数字が明らかになりました。これは全産業平均と比較してどうなのか、そしてなぜこのような状況が生まれているのか。この記事では、20,699名もの介護職員から集められた貴重なデータをもとに、労働時間、残業、有給休暇の実態を徹底解剖します。さらに、職位による格差や改善のためのヒントまで、あなたの職場環境を見直すきっかけとなる情報をお届けします。
介護職の労働時間の実態週40時間超が半数以上

介護のイメージ
介護労働安定センターが令和5年10月に実施した調査によると、介護職員の働き方には明確な特徴が見られました。まず注目すべきは、1週間の平均勤務日数が「5日」と回答した人が75.4%を占めている点です。これは一般的な週休2日制に相当し、介護業界でも標準的な勤務体系が定着していることを示しています。
しかし、勤務時間数を見ると状況は少し複雑です。1週間の平均勤務時間が「40~44時間」と回答した人が50.4%と、全体の半数以上に達しました。平均勤務時間は36.9時間でしたが、最短1.0時間から最長104.0時間まで、職場や雇用形態によって大きな開きがあることが分かります。
職種別で見ると、最も勤務時間が長いのは生活相談員で40.6時間、次いでサービス提供責任者が39.8時間、介護支援専門員が38.5時間という順になっています。これらの職種は利用者や家族との調整業務、書類作成など、直接的な介護以外の業務が多いことが長時間労働の要因となっているようです。パートタイム職員を含む平均値であることを考えると、フルタイムで働く職員の実態はさらに長時間に及んでいる可能性があります。
残業時間の現実管理職は一般職の7倍以上
介護の現場における残業の実態も、今回の調査で詳しく明らかになりました。興味深いのは、「残業なし」と回答した人が57.7%と過半数を占めている点です。これに「5時間未満」の24.3%、「5~10時間未満」の9.7%と続き、多くの介護職員は比較的残業が少ない環境で働いているように見えます。
平均残業時間は1.6時間で、最長でも48.0時間という結果でした。しかし、ここで見逃してはならないのが職位による大きな格差です。管理職の平均残業時間は3.0時間で、他の職位と比較して明らかに長くなっています。さらに注目すべきは、週15時間以上の残業をしている割合が、管理職では3.0%、主任・リーダー職では1.1%、一般職では0.4%と、職位が上がるほど長時間残業の比率が高まっている点です。
これは、管理職になると利用者対応だけでなく、スタッフのシフト管理、行政への報告書作成、家族対応、事業所運営に関わる業務など、多岐にわたる責任が発生することが原因と考えられます。キャリアアップを目指す介護職員にとって、この現実は大きな悩みの種となっているでしょう。
有給休暇取得率53.7%が示す深刻な課題
今回の調査で最も注目すべきポイントが、有給休暇の取得率です。新規付与日数に対する取得日数の割合を見ると、「40~60%未満」が24.0%で最も多く、次いで「20~40%未満」が21.9%、「100%以上」が16.9%、「60~80%未満」が14.5%という結果になりました。全体の平均取得率は53.7%です。
この数字をどう捉えるべきでしょうか。厚生労働省の調査によると、令和4年の全産業における年次有給休暇取得率は約58.3%でしたので、介護業界は全産業平均よりもやや低い水準にあると言えます。しかし、より深刻なのは取得率のばらつきです。100%以上取得している人が16.9%いる一方で、20%未満しか取得できていない層も相当数存在しているのです。
さらに問題なのが、職位による取得率の差です。管理職の取得率は48.3%、主任・リーダー職は52.0%、一般職は56.2%と、職位が上がるほど有給を取りにくくなる傾向が明確に表れています。責任ある立場になるほど、「自分が休むと現場が回らない」「スタッフに示しがつかない」というプレッシャーから、有給取得を躊躇してしまう実態が浮き彫りになっています。
なぜ介護職は有給を取得しにくいのか
介護業界で有給取得率が伸び悩む背景には、いくつかの構造的な要因があります。最も大きいのは慢性的な人手不足です。ギリギリの人員配置で運営している事業所も多く、一人が休むと他のスタッフに負担がかかってしまうため、罪悪感から休みを申請しにくい雰囲気が生まれています。
また、介護は利用者の生活を支える仕事であるため、「自分が休んだら利用者さんに迷惑がかかる」という強い責任感も、有給取得のハードルを上げています。特に担当制を採用している施設では、自分の担当利用者のケアを他のスタッフに任せることへの抵抗感が強くなりがちです。
さらに、シフト制勤務という働き方の特性も影響しています。1ヶ月前にシフトが決まってしまうと、急な予定が入っても有給を使いにくい状況が生まれます。加えて、管理職や中堅職員は会議や研修、緊急時の対応など、予定外の業務が入りやすく、計画的な休暇取得が困難になっているのです。
有給取得率を改善するための具体的な方法
有給取得率を向上させるためには、個人の努力だけでなく、組織全体での取り組みが不可欠です。まず効果的なのが計画年休制度の導入です。年度初めに有給取得の計画を立て、スケジュールに組み込んでおくことで、「いつ休むか」という心理的ハードルを下げることができます。
また、管理職自らが率先して有給を取得することも重要です。上司が休まない職場では、部下も休みにくい雰囲気が醸成されてしまいます。管理職が積極的に休暇を取り、その間も業務が回る体制を作ることで、スタッフ全員が安心して休める文化が育ちます。
人員配置の見直しも欠かせません。最低限の人数ではなく、有給取得を前提とした余裕のある配置を行うことで、誰かが休んでも業務に支障が出ない体制を構築できます。また、担当制と非担当制のハイブリッド運用を導入し、誰でも利用者のケアができる環境を整えることも有効です。
デジタル技術の活用も見逃せません。介護記録のICT化やコミュニケーションツールの導入により、情報共有がスムーズになれば、担当者が不在でも他のスタッフが適切に対応できるようになります。業務の効率化により生まれた時間を休暇取得に充てることも可能になるでしょう。
職位別に見る有給取得の戦略
職位によって有給取得の課題は異なるため、それぞれに適した戦略が必要です。一般職・担当職の方は、比較的取得率が高いものの、さらなる向上のために早めの申請を心がけましょう。1ヶ月前にはシフト希望を出し、年間行事や家族の予定も考慮した計画的な取得を目指すことが大切です。
主任・リーダー職の方は、チームマネジメントの一環として有給取得を捉えてください。自分が休んでも業務が回る仕組みを作ることは、リーダーとしての重要なスキルです。後輩育成のチャンスと考え、不在時の業務を任せることで、チーム全体の能力向上にもつながります。
管理職の方は、最も取得率が低い層ですが、だからこそ意識的な取り組みが必要です。副管理者や主任との権限委譲を進め、自分がいなくても運営できる体制を整えることが先決です。また、月に1回は必ず有給を取得するなど、自らルールを設定することも効果的でしょう。
介護職有給休暇実態調査に関する疑問解決
介護職の有給取得率53.7%は他の業種と比べて低いのですか?
全産業平均の年次有給休暇取得率が約58%であることを考えると、介護業界の53.7%はやや低い水準です。しかし、サービス業全体で見ると決して極端に低いわけではありません。問題は、100%以上取得している層と20%未満しか取得できていない層の格差が大きい点です。職場環境によって取得しやすさに大きな差があることが、この数字から読み取れます。
管理職になると有給が取りにくくなるのはなぜですか?
管理職の有給取得率が48.3%と低い理由は、業務の性質と責任の重さにあります。管理職は緊急時の対応、行政とのやり取り、重要な意思決定など、代替が難しい業務を担っています。また、スタッフのシフト管理や運営に関わる会議など、予定外の業務も多く発生します。さらに「管理職が休むとスタッフに示しがつかない」という心理的なプレッシャーも影響しています。
有給を取得しやすい職場を見分けるポイントはありますか?
就職・転職の際に確認すべきポイントは、実際の有給取得率のデータを開示しているか、計画年休制度があるか、人員に余裕があるか(最低基準ギリギリでないか)、管理職やベテラン職員が実際に休んでいるか、などです。面接時に「スタッフの平均有給取得日数」を質問することで、その職場の文化が見えてきます。また、離職率の低い職場は、働きやすい環境が整っている可能性が高いでしょう。
パートタイム職員でも有給休暇は取得できますか?
もちろん可能です。労働基準法により、パートタイム職員にも勤務日数と勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が4日以下または週の所定労働時間が30時間未満の場合は、比例付与という形で日数が決まります。例えば、週3日勤務で6ヶ月継続勤務した場合、5日間の有給が付与されます。雇用形態に関わらず、有給休暇は労働者の権利ですので、遠慮なく取得しましょう。
今の職場に不満がある場合はどうしたらいい?
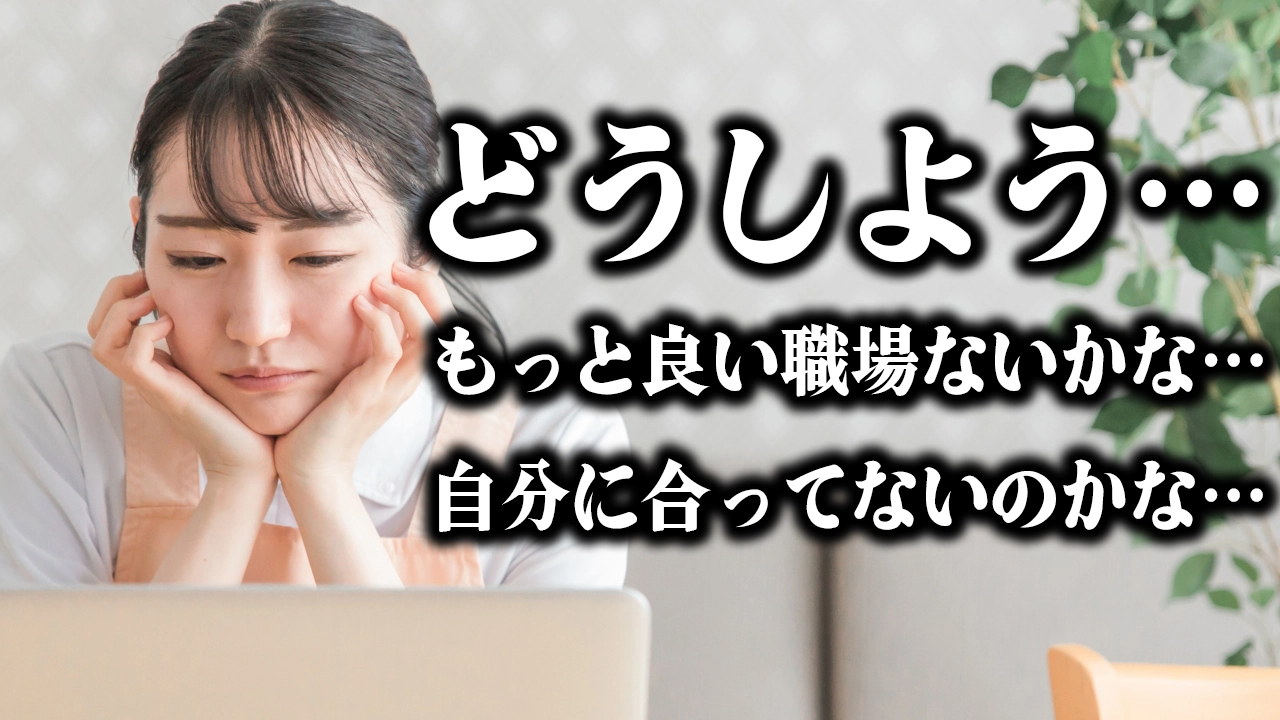
「今の待遇で満足できない」「自分をもっと評価してほしい」そう感じているあなたへ。
あなたの豊富な経験と資格は、まじめに勉強して得た努力の結晶です。
しかし、職場によってはあなたの考えが否定されたり、人間関係によって働きづらくなってしまいあなた自身が損をしてしまいます。
もし、あなたがそんな悩みを少しでも抱えているのであれば「転職」は1つの選択として、頭のどこかに入れておくことが大切です。
なぜなら、転職を1つの選択肢として、考えて動いていないと本当に自分が辛い立場や気持ちに追い込まれたときに柔軟に考えることもできなくなってしまうからです。
介護ジャストジョブは、介護業界の専門家集団として、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、待遇も働きやすさも納得できる正社員求人だけを厳選して紹介してくれます。
あなたの価値を正しく評価し、キャリアを次のステージへ押し上げる職場が見つかるサポートをしてくれている会社です。
正社員としての転職をご希望の方は今すぐご登録ください。あなたの「今」と「未来」に寄り添う転職サポートを無料で体験しませんか?
▼無料登録はこちら▼
無料登録はこちら
![]()
まとめデータから見える介護職の働き方改革
令和5年度介護労働実態調査から明らかになった有給取得率53.7%という数字は、介護業界が抱える構造的な課題を映し出しています。週40時間以上働く人が半数を超え、管理職になると残業時間が増加し、職位が上がるほど有給が取りにくくなるという実態は、決して健全な労働環境とは言えません。
しかし、この現状を変えることは可能です。計画的な年休制度の導入、管理職による率先した休暇取得、適切な人員配置、業務のICT化など、組織全体で取り組むべき施策は明確になっています。何より大切なのは、「休むことは悪いこと」ではなく「より良いケアを提供するために必要なこと」という認識を職場全体で共有することです。
介護職員一人ひとりが心身ともに健康で、やりがいを持って働き続けられる環境を作ることが、結果として利用者により質の高いケアを提供することにつながります。この調査データを、あなたの職場を見直すきっかけとして活用してみてください。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出すはずです。




コメント